老犬の痙攣は、突然の震えやピクピクとした動きに加え意識がもうろうとする様子などもあり、飼い主にとってとても心配な症状です。老犬は腎臓・肝臓の不調や低血糖といった体の衰えが原因の可能性もあり、回復に時間がかかり余命に影響することもあります。
また寒さや痛み、不安が原因の震えと見分けがつきにくいこともあります。本記事では、老犬の痙攣の見分け方や発作時の対処法、落ち着いた後の行動、受診すべきサインを整理しました。
老犬の痙攣とは

老犬が痙攣を起こす姿は、多くの飼い主にとって非常に不安なものです。突然体が震えたり、ピクピクと筋肉が収縮する姿は発作のようにも見え、心配になる方も少なくありません。
痙攣は一時的に収まる場合もあれば、繰り返し発生するケースもあり、その背景には重い病気が隠れていることもあります。また、犬は年齢によって痙攣のリスクが異なります。
若い犬では、比較的てんかんなど神経系の疾患による痙攣が多く見られますが、老犬の場合は腎不全や肝不全、低血糖といった内臓の機能低下に伴う症状として現れることが多いのが特徴です。さらに体力や免疫力の衰えにより発作は重く出やすく、回復にも時間がかかる傾向があります。そのため老犬の痙攣は単なる一時的な震えと思わず、注意深く観察することが必要です。
老犬の痙攣の詳しい症状・見分け方

老犬が痙攣を起こしたときは、体が硬直したようにこわばったり、手足をバタつかせ、痙攣するのが特徴です。意識を失ったように倒れ込み、よだれが出たり、排尿や排便を伴う場合もあります。発作は数十秒から数分で治まることが多いですが、繰り返し起きたり長時間続いたりする場合は、危険な状態の可能性があります。
一方で、老犬には体の震えもよく見られます。寒さや緊張、恐怖などで起きる震えは、小刻みなふるえが一定のリズムで続きます。震えている間も意識ははっきりしており、飼い主の声に反応したり、歩き回ることができます。これに対し痙攣は、犬自身がコントロールできず突然始まり、動きも不規則で、意識がもうろうとする点が、震えとの大きな違いです。
また、痙攣の場合は発作後にぐったりして動けなくなったり、しばらく混乱して徘徊する「発作後症状(ほっさごしょうじょう)」が見られることがあります。しかし震えでは、こうした行動変化はほとんど起こりません。
痙攣と震えを見分けるためには、「意識があるかどうか」「動きに規則性があるか」「発作後の様子がおかしくないか」などを観察することが大切です。軽い震えに見えても、意識が飛んだり、力が抜けて倒れるといった症状があれば痙攣の可能性が高いため、早めに獣医へご相談ください。
老犬が痙攣を起こした時の対処法

痙攣は飼い主にとって突然の出来事で慌ててしまいがちです。しかし慌てて誤った対応をしてしまうと、愛犬をさらに危険にさらす可能性があります。発作が起きたときにまず優先すべきは、犬の安全を確保し落ち着いて観察することです。ここでは、痙攣の最中に気を付けるべきことや、発作が治まった後にどのように対応すればよいかを具体的に解説していきます。
痙攣を起こしている最中
老犬が痙攣を起こしている最中は、飼い主が慌てず落ち着いて対応することが最も大切です。まず犬の体を無理に押さえつけたり、口の中に手を入れたりしないようにしましょう。強い痙攣によって思わず噛んでしまう危険があるため、むやみに触れないよう注意してください。さらに転倒するリスクもあるので、周囲に家具や角ばった物がある場合は、毛布やクッションを挟んで衝撃をやわらげてください。
また、発作の時間を測ることも重要です。通常30秒程度で収まることが多いですが、5分以上続く場合や、何度も繰り返す場合は命に関わる可能性があります。スマホで動画を撮影しておくと、診察時、獣医に症状を正しく伝えられるため、おすすめです。
飼い主としては心配で声をかけたくなりますが、発作中、犬はほとんど意識がないため効果はあまり期待できません。まずは二次被害が出ないよう犬の安全を確保し、発作が治まるのを待つことが最優先です。
痙攣を起こしてから落ち着いた後
発作が収まった直後の老犬は、ぐったりして動けなかったり、逆に混乱して歩き回るなど普段と違う行動を見せることがあります。この段階では無理に動かそうとせず、静かで安全な場所で安静にさせましょう。体温が下がっている場合もあるので、毛布などをかけて温めてあげると安心です。
痙攣が治まった後も、必ず症状を記録しておくことが大切です。発作が始まった時間や持続時間、痙攣の様子をメモするほか、可能であればスマホなどで動画を撮影しておきましょう。獣医の診察時に役立ちます。
また、短時間であっても発作を繰り返す場合や、回復が遅い場合は早めに動物病院を受診しましょう。落ち着いた後の観察と記録が、大切な犬にとって適切な治療につながります。
老犬が痙攣を起こす原因①病気

老犬の痙攣の背景には、体の機能低下に伴う大きな病気が隠れていることがあります。代表的なものには、てんかんや腎臓・肝臓の不調、血糖値の異常などがあり、そのままにすると発作が繰り返されたり、命に関わる場合もあります。
てんかん
てんかんは、脳内の信号が暴走し、神経のやり取りが乱れることで発作が生じる病気です。老犬の場合では、意識がふっと途切れて倒れ込む、体がこわばり大きく震える、といった症状がまとまって出やすいのが特徴です。
発作は数十秒から数分で収まることが多いですが、同じ日に何度も繰り返したり、長時間止まらない「重積発作(じゅうせきほっさ)」になると命に関わる危険性があります。
てんかんには「特発性てんかん」と「症候性(しょうこうせい)てんかん」があります。特発性てんかんは、原因がはっきりせず遺伝的な原因であるとされており、若い犬だけでなく、老犬でも見られることがあります。症候性てんかんは、脳腫瘍(のうしゅよう)や脳炎(のうえん)、脳梗塞(のうこうそく)など脳の疾患が原因で起こり、老犬では症候性てんかんの方が、割合が高い傾向があります。
発作時には、全身が硬直し手足をバタつかせたり、意識を失って倒れ込む、よだれが増える、尿や便が出てしまうといった複数のサインが同時に起こることがあります。発作後は混乱して徘徊したり、ぐったりして休むといった「発作後症状」が見られるのも特徴です。
治療には抗てんかん薬が処方され、発作の頻度や強さを抑える方法が一般的です。飼い主は「いつ・どのくらい・どんな症状だったか」を正確に把握することが重要です。
尿毒症
腎臓の機能が低下し、体に老廃物がたまることで起こるのが尿毒症(にょうどくしょう)です。老犬は加齢により腎機能が衰えやすく、慢性腎不全(まんせいじんふぜん)から尿毒症に進行するケースも少なくありません。体内に毒素が蓄積すると脳や神経に悪影響を及ぼし、痙攣や震え、意識障害といった症状を引き起こします。
尿毒症のサインには、普段より水をよく飲み尿の量が多い、体重の減少、食欲不振、嘔吐などがあります。これらが進行すると体が弱り、発作的な痙攣が現れることがあります。さらに痙攣だけでなく、慢性的な体調不良を伴うのが特徴で、腎臓の血液検査や尿検査で診断できます。
治療には点滴による老廃物の排出や食事療法が中心となりますが、重度の場合は長期的な治療が必要です。腎臓は老廃物を排出する臓器であるため、十分な水分補給はその働きを助け、症状の進行を遅らせる効果があります。また、腎機能の低下はゆっくり進むため、定期的な健診で、早めに異常を見つけることが痙攣の予防にもつながります。
肝不全
肝臓は解毒作用を担う大切な臓器で、肝機能が大きく低下すると体内にアンモニアなどの有害物質が蓄積し、脳に悪影響を及ぼします。この状態を「肝性脳症(かんせいのうしょう)」と呼び、老犬では痙攣やふらつき、意識障害を起こすことがあります。
初期の肝不全では、元気がなくなったり食欲が落ちたりと、比較的軽い症状が見られますが、進行すると黄疸(おうだん)や腹水(ふくすい)、体重減少などが現れます。そして脳に影響が及ぶと突然の痙攣や発作を引き起こしやすくなります。
治療は食事管理や薬物療法が中心で、症状に応じてアンモニアを減らす薬や点滴治療が行われます。痙攣が繰り返される場合は肝機能障害がかなり進んでいる可能性があるため、早めの受診が必要です。
低血糖
血糖値が低下すると、脳がエネルギー不足となり痙攣を起こすことがあります。若い犬ではインスリノーマ(膵臓の腫瘍)やインスリンの過剰投与で見られることが多いですが、老犬では食欲不振や内臓の不調によってエネルギー調整が乱れ、血糖値が下がることで痙攣が起こるケースがあります。
低血糖による痙攣は、ふらつき、よろけ、震えなどの前兆が見られるのが特徴です。進行すると意識がなくなり、全身の痙攣につながります。発作の合間に、はちみつや砂糖水を与えることで一時的に改善することもありますが、根本的な原因を突き止めなければ、再発を繰り返すため、必ず病院で検査を受けることが大切です。
老犬が痙攣を起こす原因②病気以外

老犬の痙攣は、必ずしも病気が原因とは限りません。寒さや痛み、精神的な不安など日常的な要因によって体が強く震えることがあり、飼い主には痙攣と区別がつきにくいケースもあります。一般的に病気以外の場合は、単なる震えであることが多いですが、症状が繰り返されたり発作のように見えるときは注意が必要です。ここでは病気以外で起こる可能性についても整理しました。
寒さ
老犬は体温調節機能が低下しているため、冬場や冷房の効いた室内では体が震えることがあります。この震えは筋肉を収縮させて熱を生み出そうとする自然な反応であり、痙攣とは異なります。震えていても意識ははっきりしており、声をかけると反応するのが特徴です。
毛布などで体を温めるだけで落ち着く場合が多いため、まずは環境を整えることが大切です。特に小型犬の老犬や毛が薄い犬種は寒さの影響を受けやすく、季節の変わり目にも注意が必要です。室温管理や散歩時の寒さ対策など、日常的な工夫が予防につながります。
痛み
老犬に多い関節炎や腰痛、歯のトラブルなど慢性的な痛みも、震えを引き起こす原因になります。強い痛みを感じた瞬間に体をこわばらせたり、小刻みに震える様子は痙攣に似ていますが、意識が保たれているかどうかで区別できます。また、痛みがある部分を触ると嫌がったり、鳴くなどの反応が見られることが多いです。
こうした場合は早めに動物病院を受診し、痛みの原因を特定して治療してあげることが必要です。特に関節や歯のトラブルは日常で見逃されやすく、気付かないうちに長く続く痛みを我慢していることがあります。日頃から、歩き方の変化や食べる様子に違和感がないかを観察してあげてください。震えの背景にある痛みのサインを、早めに見つける手がかりになるかもしれません。
精神的な不安・恐怖
老犬は若い犬より環境の変化に敏感になりやすく、大きな音や見慣れない状況に直面すると不安から震えることがあります。花火や雷、来客などがきっかけとなるケースが多く、心臓がドキドキして体が震える様子は、痙攣と勘違いされることがあります。しかしこの場合も意識ははっきりしており、飼い主の声や撫でるなどで落ち着くことが多いのが特徴です。
対処法としては、安心できる環境を整え、静かな場所で休ませてあげることが大切です。日頃から安心できる居場所を作っておくことも有効で、ハウスや毛布など「自分の場所」があると犬は落ち着きやすくなります。特定の音に敏感な場合は、防音グッズなどで音を和らげる対策もおすすめです。
老犬が痙攣を起こした時に病院に受診したほうがいいケース

- 痙攣が5分以上続く
- 1日に何度も繰り返す
- 痙攣とともに意識が戻らない。呼吸が乱れる
- 嘔吐や下痢、食欲不振など他の体調不良を伴う
- 初めて痙攣が起きた
老犬が痙攣を起こした場合、すべてが緊急事態というわけではありませんが、上記のケースに当てはまる場合は早めの受診がおすすめです。例えば痙攣が5分以上止まらない場合は「てんかん重積発作」と呼ばれ、命に関わる危険性が高くなります。また、短時間でも1日に何度も繰り返す場合も体に大きな負担となり、脳や臓器へのダメージが進行する可能性があります。
さらに、痙攣に加えて呼吸が荒い、意識が戻らないといった症状がある場合は、特に危険な状態です。嘔吐や下痢、食欲不振など他の体調不良が同時に見られる場合も、腎不全や肝不全など内臓疾患が関係していることが考えられます。
また、これまで痙攣を起こしたことがない犬に、初めて発作が見られた場合も注意が必要です。老犬は、脳腫瘍や脳梗塞などの可能性も否定できず、原因を突き止め、早く適切な治療につなげることが大切です。
飼い主としては動画やメモで発作の様子を正確に記録し、受診時に獣医へ伝えることが大切です。症状の重さを獣医に正しく判断してもらうためにも、少しでも不安を感じたら早めに相談することをおすすめします。
老犬が余命宣告された時に飼い主さんができること

愛犬が余命を宣告された時、飼い主さんの気持ちは計り知れません。できることは限られているように感じますが、最後の時間を少しでも穏やかに過ごしてもらうために、飼い主さんができることはたくさんあります。
重要なのは、「無理をさせないこと」そして「愛犬らしさを大切にしてあげること」です。
愛犬の好きなごはんをあげる
余命宣告を受けた老犬は、体調の変化によって食欲が落ちてしまうことがよくあります。食べられる量が減ったとしても、好きな匂い・食感・舌触りのごはんなら、少しでも口にしてくれることがあります。
普段より柔らかくしたりスープを足す、温めて香りを立たせるだけでも変わります。この時期は栄養バランスよりも「おいしく食べられること」が何より大切です。
好きな食事を通して、安心できる時間をつくってあげましょう。
通院の回数を増やす
症状が落ち着いているように見えても、余命期の老犬は体調が急に変化することがあります。いつもよりこまめに動物病院へ行き、獣医師としっかり相談することで不安や痛みを早めに取り除ける場合があります。
治療の目的は治すことだけではなく、苦痛を減らして残りの時間を穏やかに過ごしてもらうことにもあります。必要に応じて治療方針を変えることも、飼い主さんができる大切なサポートです。
一緒に過ごす時間を増やす
老犬にとって、飼い主さんのそばほど安心できる場所はありません。撫でてあげたり、声をかけたり、ゆっくりとそばに座っているだけでも気持ちが落ち着きます。
歩けなくなってしまっても、抱きしめてあげる、同じ布団で眠るといった過ごし方でも十分です。
残された時間が長くても短くても、飼い主さんの存在そのものが大きな支えになります。その温もりが、老犬にとって何よりの安心につながります。
老犬の痙攣に関するよくあるFAQ

老犬の痙攣は突然起こることが多く、飼い主にとってはどう対応すればよいか戸惑う場面も少なくありません。「寿命に影響するのか」「震えとどう違うのか」「軽い症状でも病院に行くべきか」など、特に質問の多い内容を取り上げ、分かりやすく解説していきます。
老犬の痙攣は余命に影響する?
老犬の痙攣そのものが直接寿命を縮めるわけではありません。しかし、痙攣の背景にある病気が腎不全や肝不全、脳疾患など重いものであれば、健康寿命に影響する可能性はあります。発作が繰り返されると体力の消耗も早まるため、原因を突き止めて早めに治療することが寿命を延ばすことに繋がります。
老犬が寝ているときにピクピク動くのは痙攣ですか?
睡眠中に足や顔の筋肉がピクピク動くのは「レム睡眠」と呼ばれる浅い眠りの状態でよく見られる現象です。夢を見ているときに起こる自然な体の反応で、痙攣とは異なります。意識があり反応できるかどうか、発作後にぐったりするかどうかで区別できます。
痙攣が軽い場合でも病院に行くべきですか?
一度だけや、数秒で収まる軽い痙攣であっても、老犬にとっては病気の初期サインであることがあります。繰り返さないか様子を詳しく観察し、できれば動画を記録して獣医に相談するのがおすすめです。発作が軽くても「初めて起こった」という事実自体が重要です。
老犬の痙攣はストレスでも起こりますか?
強いストレスや不安は、震えや一時的な筋肉のこわばりを引き起こすことがあります。これ自体は痙攣とは異なりますが、長期的なストレスが体調不良を悪化させ、間接的に発作につながる場合もあります。安心できる環境作りは、痙攣の予防にも役立ちます。
痙攣が起きた時、自宅でできる応急処置はありますか?
痙攣中にできることは限られていますが、まずは安全を確保し、床や家具の角などに頭をぶつけないよう毛布やクッションで囲むのが効果的です。発作が治まった後は安静にさせ、水分を少しずつ与えましょう。あわせて発作の様子を動画やメモで残し、正確に病院で伝えることが最大の応急処置となります。
まとめ

老犬の痙攣は、飼い主にとって非常に不安に感じる症状ですが、その背景にはさまざまな原因が潜んでいます。てんかんのような神経疾患から、腎不全・肝不全・低血糖といった内臓の不調まで幅広く、病気だけでなく寒さや痛み、精神的な不安といった原因でも震えや発作のような動きが見られることがあります。
痙攣と震えを見分けるには「意識があるか」「不規則な動きか」「発作後の様子が普段と違うか」といった観点で観察することが大切です。痙攣の最中は無理に触らず犬の安全を確保し、床や家具の角などに頭をぶつけないようにすることが第一です。治まった後は安静にさせ、動画やメモで記録を残し、獣医に正しく伝える準備をしましょう。
特に痙攣が長引いたり繰り返されたりする場合や、初めて発作が見られた時は、命に関わることもあるため、早めの受診がおすすめです。飼い主にできることは「犬の安全の確保」「正確な観察と記録」「早期の受診」の3つです。これらを意識することで、老犬の余命や快適な生活を守ることにつながります。
不安を感じる症状が見られたときは一人で抱え込まず、早めに動物病院に相談しましょう。飼い主の冷静な対応が、愛犬にとって大きな安心につながります。


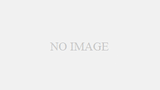
コメント