人間も加齢とともに直面する問題として認知症が挙げられますが、実は犬も認知症になることをご存じですか?
高齢になった愛犬が夜に吠えたり、寝なかったりすることは、飼い主さんにとってよくあるお悩みの一つだといえるでしょう。犬の認知症の初期症状にいち早く気づき、予防することができれば、飼い主さんの負担も軽減できる可能性があります。
この記事では、老犬の認知症の初期症状と原因について詳しく解説します。何が原因で愛犬の身体にどんなことが起こっているのか、認知症であることがわかったらどんな治療や対策がとれるのか、ぜひ参考にしてください。
犬の認知症の症状とは

犬の認知症は、正式には「認知機能不全症候群(CDS:Cognitive Dysfunction Syndrome)」と呼ばれ、加齢とともに脳の機能が著しく低下する病気です。単なる老化とは異なり、脳細胞の死滅などが原因で、人間のアルツハイマー病に似た症状が現れます。
記憶力や学習能力の衰え、周囲への認識低下など、愛犬の行動に大きな変化が見られます。この病気は8歳以上の犬の約14%に発症すると推定されていますが、関節炎や腎臓病など他の病気と症状が似ているため、見過ごされがちです。獣医師は、他の病気の可能性を一つずつ除外していく「除外診断」によって、CDSの診断を確定することが一般的です。
しかし、近年では食事に特定の栄養素を取り入れることで、病気の進行を遅らせる効果も期待されています。愛犬にいつもと違う様子が見られたら、それは認知症のサインかもしれません。早めに気づき、獣医師に相談することで、愛犬との生活の質を保つことができます。
犬が認知症になる平均年齢【余命との関連は?】
認知症を発症した犬の余命は、早ければ1〜2年ほど、長ければ3〜5年以上と、健康状態や介護の質によって大きく差が出ます。発症=余命が短くなるというわけではありませんが、進行度が早い場合や、併発している疾患がある場合は注意が必要です。
発症時期は犬種や個体差が大きいですが、加齢とともに発症率は上昇します。犬の認知症と診断された後の余命は、症状の進行度合いや健康状態によっても大きく異なるため、一概に言い切ることはできません。早期に発見し、適切なケアや食事管理を行うことで、症状の進行を遅らせ、愛犬との生活の質を維持することができます。
犬の認知症の症状チェック表
以下の項目に当てはまる場合は、認知症の可能性があります。
- 徘徊や旋回:目的もなく歩き回ったり、同じ場所をぐるぐる回ったりする。
- 夜泣き:夜間に意味もなく鳴き続ける。
- 睡眠パターンの変化:昼夜逆転し、昼間に寝てばかりいる。
- 狭い場所に入り込む:家具や部屋の隙間などに入り込み、出られなくなる。
- 反応の鈍化:名前を呼んでも反応しない、飼い主の顔を認識できないことがある。
- 食欲の異常:異常に食欲が増したり、逆に食べなくなったりする。
- トイレの失敗:トイレを覚えていたのに、失敗することが増える。
これらの症状は、脳の機能が低下することで引き起こされる行動の変化です。特に、徘徊や夜泣き、昼夜逆転は認知症に特徴的な症状とされています。食欲の変化やトイレの失敗は、他の病気でも見られる症状ですが、他の項目と合わせて当てはまる場合は、認知症の可能性が高まります。
こんな症状が出たら注意!犬の認知症の初期症状
ここでは認知症の初期症状について、詳しく解説します。愛犬の行動に当てはまるものはないか、確認していきましょう。
徘徊や旋回行動
部屋の中を意味もなくうろうろと歩いたり、ぐるぐるとただ円を描くように歩き回る旋回行動なども認知症の症状の一つです。
初期症状として、頻度が少ない場合もありますが、次第に時間を問わず体力のある限り徘徊をしたりぐるぐると旋回し続けるようになることも見られます。空間の認知能力も低下するため、部屋を歩き回って壁や角に行き当たり、抜け出せなくなってしまって飼い主さんを呼ぶこともあるでしょう。筋力が低下して歩行がスムーズにできなくなっても、徘徊や旋回行動を続けようとすることがあります。それが運動器のトラブルにつながったり、思うように動けずにストレスを感じて吠えることにつながる場合もあるのです。
留守中などは空間認知能力の低下に伴い、狭いところへ入り込んで出られなくなってしまったため、助けてもらうことができず、疲れてその場所で寝てしまうといったトラブルや、徘徊中に危険なものに接触して、けがや事故につながることもあるため、注意が必要です。
夜泣きや遠吠え
認知症の犬に多く見られるトラブルとして、夜泣きや遠吠えがあります。認知症の症状の一つである昼夜逆転などが原因で夜に吠えることが多くなります。夜泣きや遠吠えの原因として、以下のようなものが挙げられます。
- 興奮
- 不安を感じている
- 体の痛みや違和感
- 体調不良
興奮や不安を感じることは、認知症に伴う脳の変化が原因で起こるトラブルです。徘徊をすることで落ち着くケースや、声をかけて触れたりだっこをしたら落ち着くケースなど対策は様々です。
認知症による脳の変化ではなく、加齢に伴う関節の変形や筋力低下などが原因で、痛みや違和感を感じて夜間に吠えることもあります。寒さや暑さなどの不快感、体調不良による体の違和感や不快感を訴えるために吠えることも考えられます。
トイレの失敗
排泄のコントロールが上手にできなくなることも認知症の症状の一つです。
トイレの位置の認知機能の低下や排泄を我慢するなどの意識の低下などが原因となることが多いです。目の前で失敗をすれば気が付けますが、留守番中に見えないところで粗相をしていることもあります。初期症状ではトイレの失敗の頻度は少ない傾向にありますが、徐々に増えていきます。留守番中の粗相に気づきにくく、行動変化の発見が遅れてしまう場合もあるため注意が必要です。
また、認知症以外にも
- 腎不全などのトラブルによる尿量の増加
- 関節の違和感により排泄姿勢がうまくとれない
- 消化器トラブルや脱水傾向などによる便秘
など、考えられる原因は様々です。行動変化に気づいたら、認知症と他の疾患を区別するためにも、できるだけ早めに受診することを心がけましょう。
反応の低下
反応の低下も認知症によって起こる変化の一つとされています。
例えば、呼びかけにあまり反応しなくなることや、飼い主さんの帰宅などに関心を示さなくなること、遊びやおもちゃに興味を失うこと、怖がっていたものに恐怖心を示さなくなることなどが挙げられます。聴力の低下や体力の低下、運動器の機能低下なども反応の低下にはつながる可能性が高く、鑑別が必要です。
認知症が原因である場合、進行とともに反応の低下の程度も増す可能性が高いです。警戒心の強かった犬が、反応の低下により穏やかになる場合もあり、飼い主さんにとっては良い変化ととらえがちですが、認知症の可能性も高く、注意が必要です。
犬の認知症の原因|なんでうちの子が認知症に?
認知症は長生きの証でもありますが、愛犬が認知症になることを受け入れたくないと思う飼い主さんも少なくありません。認知症はなぜ起こるのでしょうか。また、どんなことが原因で起こりやすいのでしょうか。
加齢による脳の変化
認知症は加齢に伴って起こる脳の変化が関連するトラブルです。原因が明確にはわかっていませんが、人間と同じような脳の変化が起こるとされています。加齢に伴い、脳で以下のような変化が起こります。
- 脳の萎縮
- 神経細胞の減少
- βアミロイド(脳内に作られるタンパク質の一種)の沈着
βアミロイドの沈着がどの程度認知症に関連するのかは明確になっていませんが、人間でも認知症の際に脳への沈着が見られることが知られています。これらの変化に伴い、記憶力や学習能力の低下、空間認知能力の変化などの認知能力の低下が起こります。
脳の変化は不可逆であり、一度機能が低下したものを回復させることは難しいです。健康なうちから予防を行うこと、初期症状に気づいた場合は進行を遅らせられるように予防をすることが大切です。
生活習慣・環境要因
認知症の明確な原因はわかっていないものの、生活習慣や環境要因が症状の進行に大きく影響するとされています。認知症の進行を遅らせ、状態を安定させるためにより良いとされているのが、脳への刺激が期待される知育おもちゃでの遊びやトレーニング、安心感の得られる飼い主さんとのスキンシップなどです。
加齢に伴い、どんな個体でも起こり得る認知症ですが、少しでも発症や進行を遅らせるために、日常生活の中で与えられる刺激や飼い主さんとのスキンシップが欠けることで、脳への影響も考えられます。若いころから愛犬との信頼関係を充分に築き、日常生活の中で充分な刺激や安心感を得られるよう飼い主さんも努力することは大切です。
そして、より健康に長生きをできる生活習慣作りを目指すことも忘れてはいけません。
遺伝的要因
柴犬や秋田犬など日本犬は認知症になりやすい傾向があるとされています。認知症の原因が明確となっていないため、日本犬のどんなところが遺伝的に認知症につながりやすいかという点ははっきりしていません。
しかし、日本では認知症とされる犬の中の約8割が日本犬だったというデータが発表されています。世界的には犬種的な差異はないとされているため、認知症と遺伝的な要因の関係性は明確にはなっていません。
いずれ科学的に解明されることになるでしょう。現在はどんな犬でも加齢とともに起こり得る問題だと言えます。
犬の認知症予防と進行を遅らせるため、飼い主さんができること
どんな飼い主さんも愛犬には健康に長生きをしてもらいたいと願っているはずです。認知症を予防するために若いころから予防できることはどんなことなのでしょうか。そして初期症状に気づいたら行うべきことはどんなことなのでしょうか。
適度な運動と散歩
健康的な体を作り、室内外からの刺激をたくさん受け取ることが大切です。若いころから、体に負担のかからない程度の運動や散歩をすることをおすすめします。
持病があってあまり運動ができないなどの場合、カートを使用して外の音や空気に触れるだけでも充分な刺激になり得ます。体力が有り余っていて昼夜逆転して寝ない場合でも、外へ出ることで発散になり、夜間に寝てくれる可能性もあります。
季節によっては外での散歩が難しい場合もありますが、犬にとって負担にならない気候や時間帯に外に出る習慣が作れると良いでしょう。愛犬の身体の状態によっては運動制限が必要な場合もありますので、かかりつけの先生に相談しながら行ってあげてください。
脳を刺激する遊びやトレーニング
飼い主さんとの信頼関係の構築や、脳をしっかりと使う習慣をつけるために、若いころから脳を刺激する遊びやトレーニングをすることも良いでしょう。
ノーズワークなどの知育おもちゃを使用した遊びや技を教えるトレーニングなどは脳を刺激するため、認知症予防にも有意義とされています。日々の習慣にすることで、飼い主さんと愛犬の信頼関係の構築につながり、楽しみながら取り組むことができます。
室内で行うことができて、時間も問わないため、暑い夏の日や雨の日などの散歩に行けない日や、飼い主さんの帰宅が遅くて散歩に行けるタイミングが少ないなどの場合にもおすすめです。ただ、認知能力が低下してからでは、愛犬にとって難しいと感じることもあるでしょう。そのため、若い頃から習慣にしておくのがおすすめです。
バランスの取れた食事とサプリメントの活用
脳の機能低下を防ぐために、若々しい状態でいられるようにすることや、脳により良い成分を与えることはとても大切です。加齢が原因で起こる認知症にとって抗酸化作用のある成分はとても良いとされています。
抗酸化作用のある成分としては、
- ポリフェノール
- ビタミンC
- ビタミンE
などが挙げられます。ドッグフードなどにも含まれますが、より充分に摂取するために、サプリメントなどでの摂取をすることもおすすめです。
より健康な脳を作るためにDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸の積極的な摂取も良いとされています。また健康な体作りのために、バランスのとれた総合栄養食を、愛犬の体重や体格に応じて規定量しっかりと食べることと併せて、認知症への予防として働きが期待される成分を積極的に摂取するようにしましょう。
定期的な獣医師による健康チェックと早期発見
愛犬がどのような状態であるのか、定期的に健康チェックを行うことが大切です。目立った症状がなく、元気そうに見えても体内の器官の機能は低下していて、トラブルが起こりかけているということもあり得ます。
病気になってから受診をするのではなく、定期的に全身状態のチェックで検診を受ける習慣をつけましょう。見直すべき生活習慣の相談をしたり、愛犬の加齢に改めて気づくきっかけにもなるため、非常におすすめです。夜泣きや不安感など、愛犬も負担となっていることを薬を処方してもらうことで解決できるケースもあります。
行動変化に早期に気づけるのは飼い主さんだけですので、普段から愛犬の様子を観察する習慣をつけると良いでしょう。
まとめ
どんなにかわいい愛犬でも避けられないのが高齢になることであり、起こり得るのが認知症です。認知症は長生きをしてくれている証でもあります。正しい認識をし、行える予防を若くて健康なうちから行うことがとても大切です。
また、実際に認知症になったときに感じるであろう不安や対策などへの相談ができるかかりつけ医との信頼関係をしっかりと築いておくことも、安心して愛犬のシニア生活を送ることにつながります。
いずれ訪れる愛犬のシニア期のために、健康面への配慮だけでなく、食生活や生活環境づくりも早期から習慣づけておくと安心です。認知症になっても、愛犬と飼い主さんが共に幸せに、良い思い出をたくさん作れるよう、この記事がその一助となれば幸いです。


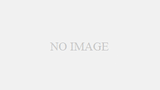
コメント