年を取りいつもとは違う呼吸姿の愛犬に、不安を感じる事はありませんか?高齢期に入った犬は、呼吸器や心臓の機能の低下がみられ、ちょっとした変化に重大なサインが隠れているんです。
「散歩後では無いのに呼吸が速い」「夜になるにつれて呼吸が荒い」など、普段との違いに気づくとどうすればよいのか戸惑ってしまいます。
犬の呼吸は、体調を知るうえで非常に重要なバロメーターと言われています。この記事では、老犬の呼吸に関する基本知識や注意すべき症状、異常の見分け方に加え、家庭内でも行えるケア方法や病院に行くまでの応急対応もご紹介します。
老犬の呼吸が早い・息が荒い時によくある原因【病気が原因】
犬は年齢を重ねると、体のあちこちに小さな変化が現れるようになります。そのひとつが「呼吸の変化」です。若い頃には気にならなかった呼吸の速さや浅さが、老犬になると目立ってくることがあります。これは心臓や肺の機能が落ちてきたり、ストレスへの耐性が弱くなったりすることが関係しています。
ここでは、シニア犬によく見られる「呼吸が早くなる主な原因」についてご紹介します。
心不全や僧帽弁閉鎖不全症
老犬に多く見られる心臓のトラブルのひとつが、「僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)」です。
これは心臓の左側にある弁がしっかり閉じなくなり、血液が逆流してしまうことで心臓に負担がかかる病気です。血液の流れが滞ることで肺に水分が溜まりやすくなり、それが呼吸のしづらさに直結します。その結果、浅くて速い呼吸が見られるようになり、夜中や寝ているときにも息苦しそうにすることがあります。
初期段階では咳や運動後の疲れやすさといった軽い症状のみですが、進行すると肺水腫など命に関わる状態に至ることもあります。早めの診断と治療を行うことで、症状をコントロールしやすくなります。
肺炎・気道疾患
年齢を重ねると免疫力が落ちやすくなり、肺炎や気管支炎といった呼吸器の感染症にかかりやすくなります。
これらの病気では、気道に炎症が起こることで空気の通り道が狭くなり、呼吸が速く荒くなる傾向があります。ゼーゼー、ヒューヒューといった異音が聞こえる場合は、気道が狭くなっているサインかもしれません。また、慢性的な咳が続くような状態は、気管支の疾患が隠れていることもあります。
さらに、小型犬では加齢によって「気管虚脱」になりやすく、これも呼吸の異常を引き起こす原因になります。普段の呼吸音の変化や咳の有無を、日常の中でこまめにチェックしておくことが大切です。
老化での基礎体力低下
特別な病気がなくても、加齢による体力の低下だけで呼吸が早くなることもあります。
年齢とともに心肺機能や筋肉量が落ちてくるため、少しの運動や温度の変化でも呼吸が乱れやすくなるのです。
また、老犬は精神的なストレスにも敏感になりやすく、ちょっとした環境の変化や体調の違和感にも強く反応し、息が荒くなることがあります。
これらは加齢による自然な変化のひとつではありますが、過度に消耗しないように生活環境を整えることが重要です。クーラーやヒーターで室温を調節したり、無理のない運動量を心がけたり、安心できるスペースを用意することで、呼吸の安定にもつながります。
鼻・のどの病気
まず、呼吸の入り口である「鼻」や「のど」にトラブルが起こると、空気の通り道が狭まり、息苦しさにつながることがあります。
鼻炎
鼻の内部の粘膜が炎症を起こし、くしゃみや鼻水、鼻づまりが見られる状態です。空気の通りが悪くなることで、犬が息をしづらくなり、呼吸音が荒くなることも。特に高齢犬では慢性化しやすく、放置すると二次的な感染のリスクも高まります。
軟口蓋過長症
短頭種(パグやフレンチブルドッグなど)に多く見られる先天的な構造の異常です。のどの奥の「軟口蓋」が必要以上に長くなっており、それが空気の通り道を塞いでしまうことで、ガーガーという音を伴った苦しそうな呼吸になります。
運動後や暑い日などに悪化しやすく、重度の場合は外科的な対応が必要になることもあります。
気管・気管支の病気
呼吸の通り道の一部である気管や気管支に異常があると、呼吸のリズムや音に変化が現れます。
気管虚脱
小型犬に多く見られる呼吸器の疾患で、気管の軟骨が柔らかくなり、呼吸時に気管がつぶれてしまう病気です。
ゼーゼー、ヒューヒューといった特徴的な音が出るほか、乾いた咳が続く場合もあります。悪化すると酸素が足りなくなり、全身に負担がかかるため、早期の診断と管理が重要です。
慢性気管支炎
長引く炎症が気管支に起こる病気で、ウイルス感染、アレルゲン、タバコの煙などの刺激が引き金になることがあります。咳き込むような症状や息切れが見られ、特に寒い日や運動後に症状が強まることも。治療には長期的なケアが必要なケースが多いです。
肺・胸の病気
呼吸器の最終地点である肺や、その周囲に異常があると、命に関わるような深刻な呼吸障害が起こることもあります。
肺炎
細菌やウイルスなどによる感染で肺に炎症が起こり、呼吸が浅くなったり、乾いた咳を繰り返すようになります。重症化すると発熱やぐったりした様子が見られ、治療が遅れると全身症状に波及することもあります。
肺水腫
心臓の働きが弱くなることなどを原因に、血液中の水分が肺に染み出してたまる状態です。これにより肺がうまく膨らまなくなり、苦しそうな呼吸を伴います。
「ガチョウの鳴き声のような呼吸音」が聞こえることもあり、これは緊急対応が必要な重大な病状です。
胸水
胸の中の空間に体液がたまり、それが肺を圧迫してしまう病態です。呼吸の動きが小さくなったり、横になれないといった様子が見られる場合があります。原因は心臓疾患や腫瘍、感染症などさまざまなため、早期の検査が必要です。
老犬の呼吸が荒くなる原因【病気以外】
犬の呼吸が荒い時、「何か病気かも?」と心配になりますが、必ずしも体調不良が理由とは限りません。犬の呼吸は、環境や体調、心理状態によっても変化する事があります。ここでは、病気ではないけれど呼吸が荒くなる代表的な理由を紹介します。
自然な体温調整は正常
犬は人間のように汗をかいて体温を下げる方法はとれません。その代わりに、呼吸を利用して熱を逃がすという仕組みを持っています。特に暑い日や運動をした後などには、口を開けて「ハアハア」と早く呼吸する「パンティング」と呼ばれる動作をします。これは犬にとってごく自然な体温調整方法で、体が熱を持ったときに冷やそうとする正常な反応です。安静にしていれば、時間とともに呼吸はゆっくりと戻っていきます。
ただし、呼吸が極端に荒かったり、よだれの量がいつもより多い・ぐったりしているといった症状を伴う場合は、熱中症の可能性も考えられますので要注意です。特に老犬は、加齢によって体温をコントロールする力が弱くなっているため、ちょっとした暑さでも息が荒くなりやすい傾向があります。室内の温度管理や水分補給をしっかり行い、愛犬が快適に過ごせるようサポートしてあげましょう。
運動後の自然な呼吸促進
犬が走ったり遊んだりした後に呼吸が荒くなるのは、体の中の必要とする酸素を補う目的で呼吸数を一時的に増やしているからです。これは運動によって体内にある酸素が一時的に不足することに対する自然な生理的反応です。特に運動量の多い犬種や、活発かつ興奮しやすい性格の犬は、運動後に「ハアハア」と激しく息をする様子が顕著に見られるでしょう。これもまた通常の範囲内であれば心配はいりません。
大切なのは、しばらく休ませたときに呼吸が穏やかに戻るかどうかです。数分〜十数分で呼吸が落ち着いてくるようであれば、病的な原因ではないと考えてよいでしょう。ただし、休んでも苦しそうな呼吸が続く場合や、他の異常が見られるときには念のため獣医師の診察を受けましょう。
不安やストレス
犬の呼吸は、精神的な影響によっても変化します。雷の音、花火、大きな工事音などに驚いたとき、あるいは留守番中や引っ越し、見知らぬ来客などがあった際に、不安や緊張から呼吸が荒くなることがあります。
このような心理的な影響による呼吸の変化も「パンティング」の一種です。恐怖心や落ち着かなさからハアハアと浅く早い呼吸をするものの、体には異常が見られず、時間の経過や安心できる環境に戻ることで自然と治まっていきます。
精神的な原因による呼吸の荒さは、食欲や元気があるかどうか、動きに不自然さがないかを確認することで見分けがつきやすくなります。特に老犬の場合は些細な環境の変化にも敏感になるため、安心できる空間づくりやスキンシップによるサポートが重要になります。
病院に行くべき老犬の異常のサインとは?
愛犬の呼吸に異変を感じたとき、どのタイミングで病院に行くべきか判断に迷うこともあるかと思います。しかし、呼吸の異常は体の中で起きている深刻なトラブルのサインであることがあり、早期の気づきが命を救うことにもつながります。特に安静にしていても呼吸が乱れているようなときは、注意が必要です。
ここでは、飼い主さんが見逃さないようにしたい「緊急性の高い呼吸異常のサイン」と、そこに隠れている可能性のある病気について詳しく解説します。
安静時でも呼吸が苦しそうな時
健康な犬は、落ち着いた状態で1分間におよそ10〜30回の呼吸をするのが一般的です。
しかし、運動をしていないにもかかわらず、それを大きく超える速さで呼吸している場合は注意が必要です。たとえば、「パンティング」とは違う、浅くて速い呼吸や苦しそうな表情を伴うような状態が見られるときは、肺や心臓に何らかの負担がかかっている可能性があります。さらに、息づかいが荒くなっているのに口を開けていない、音を立てて息をしている、という場合も異常の兆候です。
こうした呼吸は、見た目には軽度でも体内ではすでに酸素の取り込みに支障が出ている場合があります。気づいたらできるだけ早く動物病院で診てもらいましょう。
舌や歯茎が紫色や真っ白な時
犬の健康な歯茎の色は、ほんのりとしたピンク色をしています。
ところが、呼吸の異常があると血液中の酸素が不足し、「チアノーゼ」と呼ばれる症状が出て、歯茎や舌が紫や青みがかった色に変わることがあります。これは重度の呼吸不全や心臓の病気によって、酸素が十分に全身へ送られていない状態を示しています。放置すると命に関わるリスクが非常に高いため、すぐに診察を受ける必要があります。
また、歯茎が真っ白に近い色をしている場合は「貧血」が疑われます。慢性的な病気や出血、腫瘍などが原因となることがあり、こちらも早急な検査が求められます。
呼吸とあわせて口の中の色にも変化がないか、日ごろからチェックする習慣をつけておくと安心です。
横になれず座った姿勢で必死に呼吸している時
犬がいつもと違う体勢で呼吸しているとき、それは異常を訴えるサインかもしれません。
とくに、横になることができず、前足を突っ張って胸を張るような姿勢をとりながらハアハアと呼吸している場合、「起座呼吸(きざこきゅう)」と呼ばれる状態が疑われます。この姿勢は、肺や胸の中に水分がたまり、横になるとさらに呼吸が苦しくなってしまうために犬が本能的に選ぶものです。
心不全や肺水腫、胸水などの重篤な疾患が背景にある可能性が高く、すぐに対応しなければ症状が急激に悪化するおそれがあります。このような状態を見かけたときは、ためらわず動物病院へ連れていきましょう。その場での応急処置では限界があるため、早急な医療介入が求められます。
咳や失神の発作を伴う時
老犬が咳をするようになった場合、それが心臓や呼吸器の病気によるものである可能性があります。たとえば、僧帽弁閉鎖不全症では心臓が拡大し、気管を圧迫することで咳が出やすくなります。その他、気管虚脱や慢性気管支炎でも持続的な咳が見られることがあります。特に注意が必要なのは、咳が激しくなり、その直後にふらついたり、意識を失ったりするような発作がある場合です。これは、咳や病気によって脳への血流や酸素供給が一時的に不足することで起こる「失神発作」で、循環器系の重篤な異常が隠れているサインです。
こうした症状が見られた場合には、速やかに専門の診断を受け、適切な治療方針を立ててもらうことが重要です。
病院に行く前に飼い主さんができる応急処置
愛犬の呼吸が急に荒くなったとき、すぐに病院へ連れていくことが基本ですが、診察までに少し時間が空くこともあります。その間に飼い主さんができる応急対応は、愛犬の負担を軽くし、状態の悪化を防ぐうえでとても重要です。
ここでは、呼吸が苦しそうなときに家庭でできる基本的なケアについてご紹介します。
室温を25℃前後、湿度50〜60%に
呼吸が乱れている犬にとって、室内の温度や湿度の環境調整は第一に行いたい応急処置です。特に暑い季節は、気温の上昇とともに体温も上がり、呼吸への負担が増してしまいます。熱中症のリスクもあるため、エアコンや扇風機を使って室温を25℃前後に保つよう心がけましょう。
一方で、冬場は暖房を入れることで空気が乾燥しやすくなります。乾燥した空気は呼吸器に刺激を与えやすく、症状を悪化させることもあります。加湿器を使って湿度を50〜60%程度に保つことで、犬の呼吸が楽になることがあります。また、風が直接当たらないように風向きを調整したり、安心できる場所にそっと移動させたりすることも、ストレスを減らす一助になります。
水分補給をいつでもできるように
呼吸が早くなると、体から水分が失われやすくなります。特に「パンティング」と呼ばれる浅く速い呼吸が続くと、知らず知らずのうちに脱水状態に陥ってしまうことがあります。新鮮で清潔な水をすぐに飲めるように、普段よりも多めに水を用意しておくことが大切です。寝ている場所の近くや、すぐ手が届く位置に水皿を置いてあげるとよいでしょう。
また、老犬や体力の落ちた犬は、自分から水を飲みに行く気力がないこともあるため、飼い主さんがやさしく促すことも大切です。口の中や舌が乾いている、粘り気のあるよだれが出ているときは、脱水が進んでいるサインかもしれません。どうしても水を受けつけない場合は、獣医師に相談のうえでスポーツドリンクのような電解質を含んだ補水液を使用することも検討されます。
呼吸状態・回数・持続時間をメモしておく
病院で正確な診断を受けるために、呼吸の状態を記録することはとても役立ちます。特に、いつから呼吸が荒くなったのか、どのくらいの時間続いているのか、ほかに気になる症状(咳・失神・食欲低下など)があったかを具体的に書き留めておくことで、獣医師が状況を正しく把握しやすくなります。
また、呼吸数もできれば測っておきましょう。愛犬が落ち着いているときに、胸やお腹の上下運動を数えて1分間の呼吸回数を確認します。難しい場合は15秒測って4倍、30秒で2倍にして計算してもかまいません。呼吸音や体の震え、姿勢の変化なども可能な範囲で観察し、記録しておくと診察時の判断材料としてとても有効です。スマートフォンで動画を撮っておくのも、実際の様子を伝える良い手段になります。
正常時の犬の呼吸について
犬の呼吸数は、体格や年齢、環境温度といった要因により多少の差がありますが、健康な状態ではおおよそ1分間に10〜35回が目安とされています。
小型犬は代謝が活発で体温も高めな事もあり、呼吸数がやや多くなる傾向を認めます。一方で、大型犬の場合は1分間に15〜25回程度が一般的です。季節や気温の影響も受けやすく、暑い時期には体温調節のために呼吸が増えることもあります。また、子犬の場合も同様に、成犬よりもやや呼吸が速いことが多いです。
基本的に、犬はリラックス時にはゆっくりと鼻から呼吸をしており、口を閉じているのが通常の状態です。口を開けたまま速く呼吸していたり、苦しそうに見える場合は、注意が必要になることもあります。
犬の呼吸の測り方
愛犬の呼吸を確認する際には、まずできるだけ静かで落ち着いた状態のときを選びましょう。散歩の後や興奮中は呼吸が早くなっており、参考になりにくいことがあります
測定の具体的な方法は、犬の胸やお腹の上下する動きを観察するのが基本です。膨らんでへこむ動きを1回とカウントし、それを1分間計測することで呼吸数を知ることができます。1分間じっとしているのが難しい場合は、30秒で数えた回数を2倍、あるいは15秒で測って4倍に換算する方法でも問題ありません。
また、被毛が長くて動きが見えにくい犬種の場合は、鼻の前に小さな鏡を置き、曇りの回数を数える方法も使えます。特に夜間や就寝中など、飼い主さんが気になるタイミングで確認できるように、日頃からやり方を覚えておくと安心です。
老犬の呼吸が早いに関するよくある質問
愛犬の呼吸が早いと感じたとき、「これって異常なの?」「病院に連れて行くべき?」と悩む飼い主さんは多くいます。特に高齢の犬では、日々の変化を見逃さず、疑問を持つことが大切です。老犬に多く見られる呼吸に関するお悩みや、飼い主さんが知っておきたい基礎知識をまとめました。
犬の異常な呼吸音はどんなものがありますか?
犬の呼吸音に異常がある場合、以下のような特徴的な音が聞かれることがあります。
高調スターター音(スースー、キューキュー)
鼻や喉の奥の硬い部分が狭くなったときに出る音で、鼻腔狭窄や鼻腔内の腫瘍などでよく見られます。
低調スターター音(ズーズー、ブーブー)
軟口蓋などの柔らかい組織が気道をふさぐことで生じます。短頭種気道症候群や軟口蓋過長症の犬に多く見られます。
ストライダー音(ガーガー、ヒューヒュー)
喉頭や気管の部分で空気の通り道が狭まったときの音。気管虚脱や喉頭狭窄の可能性があります。
ゴロゴロ・ブツブツ音
気道内に痰や分泌物がたまったときに聞こえることがあり、慢性気管支炎や肺水腫で見られる症状です。
こうした呼吸音が聞こえた場合は、なるべく早めに動物病院で診察を受けましょう。
心臓病の犬の呼吸はどう違いますか?
心臓に問題がある犬では、呼吸のリズムが乱れたり、常に浅く速くなる傾向があります。
加えて、乾いた咳が続く、夜中に呼吸が苦しくなる、運動後に疲れやすくなるといった症状もよく見られます。重症化すると、舌や歯茎が紫色っぽくなる「チアノーゼ」や、一時的に意識を失う「失神発作」が起こることも。心臓病は進行性の疾患が多いため、日頃から呼吸の様子を観察し、小さな変化を見逃さないことが大切です。
呼吸が荒い老犬に普段から気をつけるべき生活習慣は?
呼吸が不安定になりやすい老犬には、日常生活の環境を整えることがとても重要です。
室温は25℃前後、湿度は50〜60%を保ち、暑すぎたり寒すぎたりしないように調整しましょう。また、過度な運動を避けつつ、散歩などで適度に体を動かすことも大切です。体力が落ちすぎると呼吸器にも影響が出ます。
静かで安心できる空間を確保し、ストレスを感じにくい環境を作ってあげることも予防につながります。定期的な健康診断で、心臓や呼吸器の状態をチェックしておくことも忘れずに。
老犬が夜だけ息が荒くなるのは病気?
夜間や就寝中に呼吸が荒くなる場合、心臓や肺の疾患が背景にある可能性があります。
特に小型犬に多く見られる「僧帽弁閉鎖不全症」は、夜間に症状が強く出ることが多く、見逃されがちです。夜間の呼吸困難は、体を横にすると肺に負担がかかることが一因とも言われており、進行した心不全や肺水腫の兆候であることもあります。こうした症状が続くようなら、日中は元気に見えていても、できるだけ早く獣医師に相談することをおすすめします。
老犬の呼吸異常は予防できますか?
完全に防ぐことは難しいものの、日常の生活習慣を見直すことで予防や進行の遅延が可能です。
たとえば、体重を適正に保つことで、心臓や気道への負担が軽くなります。特に短頭種は太りやすく、呼吸に影響が出やすいため注意が必要です。また、暑い季節には熱中症対策を徹底し、無理な運動を避けることも大切です。定期的な健康チェックで、早い段階から異常を見つけることができれば、対処もしやすくなります。
まとめ
老犬の呼吸が普段よりも速くなる背景には、年齢による心肺機能の低下だけでなく、心不全や気道疾患などの病気が潜んでいることもあります。安静時でも呼吸が荒い、咳や失神を伴う、舌の色が青白くなるといった症状が見られる場合は、できるだけ早く獣医師の診察を受けましょう。
また、室温管理や水分補給、呼吸の記録といった家庭での対応も、愛犬の負担を軽くし、的確な診断につなげる重要なステップです。小さな異変にいち早く気づけるよう、日々の観察とケアを丁寧に続けていきましょう。


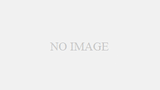
コメント