犬のクッシング症候群は副腎皮質ホルモンが出過ぎることで起こる病気です。病気が進むと初期症状で見られた多飲多尿や食欲亢進、中期症状の脱毛や腹囲膨満といった症状が出現し、さらに深刻な状態になります。
末期には免疫力がかなり低下するため、感染症にもかかりやすく、いったん発症すると重症化しやすいのが特徴です。
屈伸症候群は犬の生活の質を著しく低下させることから獣医さんとよく相談しながら症状を和らげ、初期段階から感知に向けて治療することが愛犬にとって一番大切です。
そこで今回は、犬のクッシング症候群について説明しましょう。
犬のクッシング症候群とは?

犬のクッシング症候群、別名「副腎皮質機能亢進症」は、ホルモンの病気です。
腎臓の近くにある副腎という場所から出る「コルチゾール」が長い間出過ぎてしまうと、体に多くの良くないことが起こります。
普段と違う様子が見られるのが特徴です。例えば極端に食欲が増えたり、水をたくさん飲むようになったり、毛が抜けたり、元気がないといったことから気づくこともあります。
ここでは、この病気の仕組みと主な原因を簡単に説明します。
完治が難しい病気の一つ
犬のクッシング症候群は別名「副腎皮質機能亢進症」と呼ばれる内分泌系の疾患で、特に中高齢の犬によく見られます。副腎という腎臓の近くにある小さな臓器から分泌されるコルチゾールは、本来、ストレス反応や代謝調整に不可欠なホルモンです。
しかし、脳下垂体や副腎に腫瘍ができると、ホルモンバランスが崩れ、コルチゾールが慢性的に過剰に分泌されます。この状態が続くと筋力低下をはじめ皮膚が薄くなる、免疫力低下、糖尿病など様々な症状が現れます。
加えて、ステロイド剤の長期使用も同様の状態を引き起こすことがあります。この病気は完治が難しく、生涯にわたってコルチゾールの過剰分泌を抑える薬を投与して症状を管理することが主な治療となります。早期発見と定期的な検査が大切で特にプードル、ダックスフント、ビーグルなどの中高齢犬は発症しやすいとされています。
犬がクッシング症候群になる原因

犬のクッシング症候群は、ストレスホルモンであるコルチゾールが体内で過剰に作られることで起こります。
原因はいくつか考えられますが、一番多いのは脳の下垂体にできる腫瘍です。他に副腎そのものに腫瘍ができたり、薬の副作用で発症したりするケースもあります。そして、原因によって治療方法やその後の経過が変わってきます。
ここでは主な原因について解説しましょう。
下垂体腫瘍
犬のクッシング症候群で一番多いのは「下垂体性」のものです。これは脳の下垂体に良性の腫瘍ができて、そこから副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)というホルモンが出過ぎてしまう状態を指します。
ACTHが過剰に出ると副腎が刺激されてコルチゾールが大量に作られ、ホルモンバランスが崩れます。その結果として水をたくさん飲んで尿がたくさん出る、食欲が異常に増す、毛が抜けるほかにお腹が膨れるといった症状が出やすくなります。
症例の8割から9割はこのタイプで、腫瘍が大きくなると視覚がおかしくなったり、行動が変わったりするなどの神経症状が出ることもあります。治療法としては、薬を使う方法や放射線療法があります。
副腎腫瘍
次に多いのは「副腎腫瘍」が原因の場合です。これは、副腎に腫瘍ができて、そこからコルチゾールが過剰に分泌される状態を指します。この場合、脳の下垂体には異常がないのに、体内のコルチゾール濃度が高くなってしまいます。
副腎腫瘍の約半分は良性なので、手術で腫瘍を取り除けば完治する可能性があります。ただし、悪性腫瘍(副腎皮質がん)の場合は転移しやすく、手術が難しいこともあります。
CT検査や超音波検査などで腫瘍の位置や状態をよく調べてから慎重に治療方法を決めることが大切です。
薬の長期使用
3つ目の原因は「医原性クッシング症候群」というものです。
これはアトピー性皮膚炎や自己免疫疾患の治療でステロイド薬を長く、たくさん使ったことが原因で起こります。体が外から入ってくるステロイドに慣れてしまい、自分でホルモンを調整する働きが弱ってしまうのです。
このタイプは薬を減らしたり、やめたりすることで症状がよくなることもあります。しかし、急にやめると体に負担がかかるため、必ず獣医さんの指示に従って行ってください。薬の使い方や量をきちんと管理することが再発を防ぐことにつながります。
犬のクッシング症候群の症状は?初期から末期まで

犬のクッシング症候群は、副腎皮質ホルモンの一種であるコルチゾールが過剰に分泌される病気です。コルチゾールは、ストレスや代謝の調整に不可欠ですが、多すぎると体に悪い影響が出ます。
症状は徐々に進むため、「年のせいかな?」と思われがちで、発見が遅れることも。
ここでは、初期、中期、末期に現れる症状の変化をわかりやすく説明します。
初期症状
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)の初期は、飼い主さんが見過ごしがちな、ちょっとした変化から始まります。よくあるのが水をたくさん飲んで、おしっこの回数が増えることです。
「ペットシートの交換が前より増えた」「夜中にもトイレに行くようになった」と感じたら注意が必要です。くわえて食欲がすごく増すのも特徴です。今まで欲しがらなかった物を欲しがったり、ゴミ箱を漁ったりするかもしれません。
この段階で皮膚の変化はまだ軽いことが多いですが、毛が薄くなったり、皮膚がちょっと透けて見えるようなサインが出始めることもあります。体重は少し増えることが多いですが筋肉が減っているかどうかは、まだわかりにくいでしょう。
もし初期の段階で気づいて検査を受ければ、早めに治療を始めることで、病気の進行を抑えられることがあります。
中期症状
病気が進むと症状がもっとハッキリ出て、見た目にも変化が出てきます。その中でも目立つのは「お腹の膨らみ」です。内臓脂肪が増えたり、腹筋が弱くなったりして、お腹が垂れてきます。
筋肉もどんどん落ちてきて階段を上るのを嫌がったり、散歩の途中で座り込んだりして、体力の低下が目立つようになります。さらに皮膚も乾燥しがちでフケやかゆみが出たり、バイ菌が入って炎症を起こしやすくなったり、ケガが治りにくくなったりします。
また、「パンティング」と呼ばれる浅くて早い呼吸を頻繁にするようになったり、夜中に呼吸が荒くなる犬もいます。体の抵抗力も落ちて、膀胱炎とか皮膚炎を何度も繰り返すことも少なくありません。
この時期になると、見た目とか行動の変化がハッキリしてくるので、病気を疑うきっかけになることも多いです
末期症状
クッシング症候群が末期になると、全身に深刻な症状が出ます。
筋肉が落ちて足腰が弱り、転びやすくなったり、歩きにくくなったりします。さらに体重が減って、すごく疲れやすくなり、活動量が急激に減ることも。
皮膚がさらに薄くなって皮膚の中に白い斑点が出たり、潰瘍ができたりと、ひどい状態になることもあります。また、内臓にも負担がかかり高血圧や糖尿病、腎不全さらには急性膵炎といった病気を併発しやすくなります。こういった合併症は命に関わることも多く、治療をしても、残念ながら余命が数ヶ月から1年程度になることも珍しくありません。
末期では、命を長くすることよりも、痛みや不安を和らげて、生活の質を保つことが重視されます。飼い主さんがそばにいて、穏やかな時間を一緒に過ごすことが何よりも大切です。
すぐに受診すべきクッシング症候群の末期症状とは

犬のクッシング症候群は、ゆっくりと時間をかけて進行する病気です。しかし、末期になったり、急に具合が悪くなったりすると、命に関わることもあります。
だからこそ、飼い主さんが早く気づいて、すぐに対応することが大切です。
ここでは、特に気をつけたい末期の症状について、その理由も含めて詳しく説明します。
突然の呼吸困難
クッシング症候群でコルチゾールが高い状態が続くと、高血圧になりやすくなります。この高血圧が心臓、特に左心室に大きな負担をかけます。その結果うっ血性心不全になり、血液が肺に溜まって肺水腫を起こすことがあります。肺水腫になると、ガス交換がうまくいかなくなり、急に呼吸が苦しくなります。
またクッシング症候群では血液が固まりやすいので、肺動脈血栓塞栓症のリスクも高まります。血栓が肺の血管を塞ぐと、急に酸素が足りなくなり、チアノーゼ(歯茎や舌が紫色になる)を起こしてショック状態になることもあります。
加えて、免疫力が下がることで肺炎を併発しやすく、呼吸が速く浅くなることがあります。
これらの症状が見られたら、すぐ獣医さんによる集中治療(利尿剤、抗凝固療法、呼吸補助)が必要です。
急激な意識レベルの低下・昏睡状態
クッシング症候群は、全身の代謝、循環、神経に大きく影響します。
例えばコルチゾールが過剰になると、インスリンの効きが悪くなり、重い糖尿病やケトアシドーシスになることがあります。こうした代謝の異常は脳の働きにも悪影響を及ぼし、意識障害や昏睡の主な原因となります。
また高血圧が続くと「高血圧性脳症」になることもあり、脳の血管が傷ついて脳がむくんだり、出血したりすることがあります。急に意識が悪くなるのは、脳への酸素不足や低血糖、電解質異常、アシドーシスなどの代謝異常が原因で、命にかかわるサインです。
脳は酸素やブドウ糖が数分間途絶えるだけで、回復できないダメージを受けるため、すぐに治療(輸液、血糖補正、酸素投与、血圧管理など)を受けなければなりません。
もし意識がぼんやりする、反応が鈍いほかに立てないといった変化が見られたら、すぐに病院を受診してください。
激しい嘔吐・下痢と腹部の痛み
クッシング症候群の犬では、コルチゾールの過剰によって胃腸の粘膜防御力が著しく低下します。そのため、胃酸による刺激で胃潰瘍や十二指腸潰瘍が起こりやすく、さらに進行すると穿孔(穴が開く)を起こすこともあります。
またステロイドの影響や高脂血症の合併により、胆嚢炎や膵炎といった急性腹症を発症するケースも多く見られます。激しい嘔吐や下痢は、体液と電解質の急速な喪失を意味し、重度の脱水症やショックを引き起こすことも少なくありません。
さらに強い腹痛を伴う場合は、すでに消化管穿孔や敗血症性ショックが進行している可能性があります。
このような症状が現れた場合は、点滴・抗生物質・電解質補正・緊急手術など、迅速な対応が求められます。
放置すると多臓器不全に進行する恐れがあるため、すぐに動物病院を受診してください。
高熱または重度の低体温
クッシング症候群になると、コルチゾールが過剰になり免疫力がかなり下がります。
そのため細菌、ウイルス、カビなどに感染しやすくなり、軽い感染症でも肺炎や敗血症に急に悪化することが少なくありません。敗血症は全身の臓器に炎症を起こして高熱、頻脈、呼吸が速くなるなどの症状が出ます。すぐに命に関わる状態になることも多いのです。
逆に、体温が異常に下がる「低体温」も非常に危ないサインです。これはショックや循環不全、全身の代謝機能がうまく働かなくなっているサインで体温を調節する機能が麻痺している可能性があります。
重度の低体温は敗血症の末期や心臓の機能が低下しているときにも見られ、すぐに体を温めたり、輸液をしたり循環を助ける必要があります。
もし高熱、寒気、震えまたは異常に体温が低いと感じたら、すぐに獣医さんに診てもらうことが大切です。
犬がクッシング症候群の末期症状になってしまった時の治療

クッシング症候群は、徐々に進行する病気で末期になると合併症や症状が悪化し、犬の生活の質が大きく下がってしまいます。
しかし、末期の症状が出てきたからといって諦める必要はありません。適切な治療とケアで、犬の苦しみを和らげて少しでも長く、そして快適に過ごせるようにしてあげられます。
ここでは、末期症状が出た後でもできる主な治療法と飼い主さんができるサポートについて説明します。
手術療法
副腎に腫瘍がある場合、手術でその副腎ごと摘出すれば完治を目指せる可能性があります。
この手術は原因を取り除く治療法ですが、とても専門的な技術が必要です。そのため、しっかりした設備と経験豊富な獣医さんの元で行う必要があります。手術後、ホルモンバランスが急に変わることがあるので、副腎皮質ホルモンを補充する必要が出てくるかもしれません。
さらに腫瘍の大きさや場所、それに犬の年齢や体の状態によっては手術が難しいこともあります。
そのため、手術のリスクやどれくらい回復が見込めるかなど獣医さんとよく話し合って、手術以外の方法も考えてみることが大切です。
薬物療法
犬の下垂体性クッシング症候群で手術が難しい時は、薬での治療がメインになります。よく使われるのは「トリロスタン」という薬で、これは副腎から出るコルチゾールを抑えるものです。
この薬で症状が楽になり、ホルモンバランスも安定するため多くの犬で生活の質が上がります。ただし、薬の量は犬の体重や体調に合わせて細かく変える必要があり、多く飲ませすぎると副作用が出ることもあります。
そのため定期的に血液検査をして、コルチゾール値をチェックしながら安全に治療を続けることが大切です。治療は長くなることが多いので、飼い主さんのサポートも必要です。
放射線療法
下垂体腫瘍が大きくて手術が難しい場合や神経症状が出ている場合は、放射線治療という方法もあります。
放射線を使って腫瘍の成長を抑えてホルモンが出すぎるのを防ぐことで、症状を軽くすることができます。また、脳への圧迫が減ることで視力低下やふらつきといった神経症状が悪化するのを防ぐことも期待できます。
ただ、放射線治療ができる動物病院は少なく治療には何度か通院する必要があり、お金もかかります。それに犬によっては食欲不振や疲れといった副作用が出ることもありますので、事前に先生から十分説明を受けておくことが重要です。
生活改善の指導
犬が末期になったら、治療と並行して生活のケアをすることも大切です。
食事は脂肪分が少なく、質の高いタンパク質を中心にするのがおすすめです。糖分や塩分を控えれば、体の負担を減らせます。高血圧や糖尿病にならないように栄養バランスを考えたドッグフードを選びましょう。散歩などで無理なく体を動かしたり、静かな環境でゆっくり休ませてあげることも重要です。
ストレスはホルモンバランスを崩すので飼い主さんが穏やかに接することも、治療の一環になります。
こういった日々のケアをきちんと行うことで、症状が悪化するのを抑えて少しでも快適に過ごせるようにしてあげましょう。
クッシング症候群の末期症状が出てから余命は?

犬のクッシング症候群はゆっくり進行する病気で、末期には臓器に問題が出たり、他の病気を併発したりして急に悪化することがあります。
どれくらい生きられるかは治療をするかどうか、病気がどれだけ進んでいるかで大きく変わります。十分な治療をすれば、生活の質を良くしたり、寿命を延ばしたりすることもできます。
ここでは、治療をした場合としない場合で、どれだけ寿命が変わるのかを詳しく説明します。
治療をしない場合の余命の目安
犬がクッシング症候群を放置すると、寿命は短くなることがほとんどです。コルチゾールが過剰に出続けると体の色々な臓器に負担がかかり、病気が進んで行くからです。
免疫力が下がることで皮膚炎や尿路感染症が悪化しやすく糖尿病、膵炎、高血圧、血栓症といった命取りになる合併症も起こりえます。さらに血栓が肺動脈に詰まると、突然死につながる危険性があります。
ある研究では、治療しなかった犬の生存期間の中央値は約178日(約6か月)と報告されています。そして、多くの犬が診断から数か月~1年以内に亡くなっています。
治療をしないと症状の進行を止めるのは難しく、早めの対応が大切です。
治療をした場合の余命の目安
犬が適切な治療を受けると、治療なしの場合よりも寿命がかなり延びます。ある報告では治療後の中央生存期間(MST)は約521日(1年半強)とされ、治療しない場合の約3倍になるとのことです。
病気の種類によって差があり、下垂体性の場合は主に薬を使った治療が中心です。この治療を行えばMSTは662~900日(約1年半~2年半)と比較的良好です。一方、副腎性の場合は手術や薬物療法が選ばれ、MSTは353~953日と幅があります。
さらに腫瘍を摘出手術で取り除くことができた場合は、4年以上生きることもあります。治療によってコルチゾールの分泌が抑えられ、他の病気になるリスクが減ることで生活の質(QOL)が上がり、穏やかな生活を送れるようになります。
犬のクッシング症候群に関するよくある質問

寿命や生活の質を保つには、正確な診断と適切な治療、そして日々のケアがとても大切です。
ここでは犬のクッシング症候群について飼い主さんが気になる診断方法、終末期のケア、治療費などをわかりやすく説明します。
クッシング症候群の診断はどのように行うのですか?
まず、視診、触診、問診で症状をチェックして血液検査や尿検査を行います。もし肝酵素(ALP)が上がっていたり、血中コルチゾール値に異常があれば、ACTH刺激試験や低用量デキサメタゾン抑制試験でホルモンの反応を見ます。
さらに超音波検査で副腎の大きさや腫瘍がないか確認し、必要であればCTやMRI検査で詳しく調べます。
末期症状が出ても生活の質を保つためのポイントはありますか?
犬が終末期を迎えてもできる限り痛みや不快感を和らげて穏やかに過ごさせてあげることが大切です。
獣医さんと相談しながら、鎮痛剤を使ったり、栄養バランスの取れた食事を用意したり、ストレスの少ない環境を整えたりしてあげましょう。
また、必要に応じて薬での治療やリハビリも検討し、心身ともに安定した状態を保てるようにサポートします。飼い主さんが優しく声をかけたり、スキンシップをすることも犬の安心感につながり、生活の質を高めるために重要です。
末期症状が出たらどんな食事にすればいいですか?
末期症状が出る終末期には消化しやすく、効率的にエネルギーを補給できる食事が望ましいです。質の良いタンパク質と適度な脂肪を中心に、低脂肪・低炭水化物の療法食を検討しましょう。
獣医さんと相談して栄養補助食品を使うのも良い方法です。脱水にならないようにしっかり水分を摂らせ、口の中を清潔に保つことも大切です。体調に合わせて食事を柔軟に変えていきましょう。
薬物療法による副作用が出たときにはどうすればいいですか?
薬の副作用として吐き気、下痢、食欲不振、肝臓のトラブルなどが起こることがあります。もしそのような症状が出たら自分で判断せずに、すぐに獣医さんに相談してください。
獣医さんが状況を見て薬の量を調整したり、種類を変えたり、一時的に薬を止めるなどの対応をすることがあります。さらに定期的な血液検査や様子観察をきちんと行い、副作用を早く見つけて適切に対処することで症状が悪化するのを防ぐことが大切です。
末期の治療にはどのくらいの費用がかかりますか?
治療にかかるお金は、どんな治療をするか、どこの病院に行くかで大きく変わります。飲み薬での治療なら、およそ月に数千円から1万円くらいでしょう。
手術をすると入院のお金も入れて、総額で数十万円になることもあります。さらに放射線治療や特別な検査も一緒に実施すると全部で数十万円から100万円以上になることもあります。そのため治療を始める前に、どんな治療にどれくらいお金がかかるのか獣医さんにきちんと聞いておくのが大事です。
まとめ

犬のクッシング症候群は副腎から出るコルチゾールというホルモンが多すぎる病気です。よく水を飲んでおしっこをする、食欲が増す、お腹が膨れる、毛が抜けるといった症状が出ます。特に年を取った犬によく見られます。
この疾患は早く見つけて的確に診断することが大事で、ACTH刺激試験などのホルモン検査で原因を調べます。完全に治すのは難しいですが、薬や手術で症状を抑えて犬の生活の質を良くしたり、寿命を延ばしたりすることが期待できます。
様子を見て少しでもおかしいなと思ったら早めに獣医さんへ相談し、きちんとケアをしてあげてください。そうすれば、愛犬が元気に過ごせるはずです。


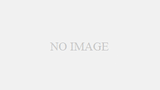
コメント