犬の鼻づまりは、放っておくと呼吸が苦しくなったりご飯を食べなくなったりする原因になるので要注意です。アレルギーやウイルス感染、何か異物を吸い込んでしまった、歯周病が悪化して膿が溜まっている、あるいは腫瘍など色々な原因が考えられます。
特にアレルギーの場合は環境の変化や特定の物質が原因になることが少なくありません。
一方で早く見つけてあげれば適切な治療や生活環境の見直しで症状がかなり楽になるでしょう。ただし原因を特定するのが難しく、長引くと治療が長くなったり、手術が必要になったりする場合もあります。愛犬のくしゃみや鼻水、いびきといったサインを見逃さないようにしましょう。
犬が鼻づまりになる時によくある原因

犬の鼻づまりは鼻の空気の通り道が狭くなったり、何かが詰まったりして起こります。よくある原因は鼻の粘膜の炎症や異物ですが感染症、アレルギー、腫瘍なども考えられます。
鼻づまりはただ不快なだけでなく、においが分かりにくくなったり、食欲が落ちたりだけでなく眠りが浅くなったりすることも珍しくありません。原因によって治療が変わるので、まずはきちんと診断してもらうことが大切です。
ここではその原因について解説しましょう。
アレルギー性鼻炎
犬も花粉、ハウスダスト、ダニ、カビといったアレルギー物質で鼻炎になることがあります。特に春や秋など季節の変わり目は要注意で水っぽい鼻水、くしゃみ、鼻づまりが繰り返し起こりやすいです。
アレルギー性鼻炎になると鼻の中の粘膜が炎症で腫れて空気の通りが悪くなるので、苦しそうに鼻を鳴らすことも。それに皮膚のかゆみや目の充血、涙が増えるなどの全身症状を伴うこともよくあります。
治療ではアレルギーの原因を取り除くことが大切で掃除や換気を工夫したり、必要なら抗ヒスタミン薬などを使ったりすることもよく見られます。
感染症
ウイルスや細菌感染で鼻の粘膜や副鼻腔が炎症を起こると鼻水、くしゃみ、鼻づまりが出ます。
犬の風邪であるケンネルコフや犬ジステンパーがよくみられる病気で特にケンネルコフは、たくさんの犬がいる場所で広がりやすいのが特徴です。
最初は軽い鼻水やクシャミだけかもしれませんが、放っておくと細菌にも感染して黄色い鼻水が出たり、熱が出たりするだけでなく食欲がなくなったりします。ひどくなると肺炎や全身に感染が広がることもあるので、早めに病院で診てもらうのが大事です。
治療は抗菌薬や抗ウイルス薬の投与やネブライザーの実施といったことがよく行われます。ゆっくり休んで、水分をしっかり摂ることも重要な治療です。
異物混入
犬が散歩や外で遊んでいる時、草の種や小石、砂、ほこりなどが鼻に入って片方の鼻だけが詰まってしまうこともよくあります。
異物が鼻に残ると炎症や細菌・ウイルスが入って、鼻水やくしゃみ、ひどい場合は鼻血が出たりもするのです。もし犬が何度も鼻をかいたり、前足で顔をこすったり、くしゃみを連発するようなら、鼻に何か入ってるサインかもしれません。
片方の鼻からだけずっと鼻水が出てるのも特徴です。自分で無理に異物を取ろうとすると鼻の中を傷つけてしまうことがあるので、動物病院で内視鏡とかで取ってもらうのが安心です。また、散歩コースとか草むらをチェックして、なるべく異物が入らないように気をつけるのも大事なポイントと言えるでしょう。
副鼻腔炎や慢性鼻炎
犬の鼻詰まりの主な原因は鼻の奥にある副鼻腔の炎症(副鼻腔炎)や鼻の粘膜に炎症が長引く慢性鼻炎です。最初は透明な鼻水が出ますが、炎症が進むとネバネバした膿のような鼻水が溜まり呼吸が苦しくなります。
ひどくなると副鼻腔に膿や血が溜まり強い息苦しさや食欲不振、発熱などを引き起こすこともあります。
原因としては以前にかかった感染症やアレルギー、歯の根元の炎症などが考えられます。鼻詰まりが長引く場合は自然に治るのを待たずに早めに動物病院で診てもらいましょう。
鼻腔内腫瘍やポリープ
犬の鼻の中に腫瘍やポリープができると鼻の通り道が狭くなるため、呼吸が荒くなったり、鼻を鳴らすなどの症状が出ます。鼻水に血が混じったり、片方の鼻だけが詰まるのもよくある症状です。
腫瘍は特に年を取った犬によく見られますが、若い犬でも起こることがあります。またシェットランド・シープドッグやコリーといった犬種は、なりやすいと言われています。
診断にはレントゲンやCT、内視鏡検査などが行われ早く見つけることが大切です。
治療法としては手術の他に放射線治療や薬を使う方法があり、腫瘍の種類や進行具合によって選びます。日頃から健康診断を受けるようにして早期発見に努めましょう。
老化による鼻の機能低下
犬も年を取ると鼻の潤いを保つ機能が衰えて、鼻の中が乾燥しやすくなります。
そのため鼻水が出にくくなり、ちょっと鼻が詰まったり、息苦しくなったりすることがあります。特に空気が乾燥する時期やエアコンをよく使う部屋では起こりやすいです。
年を取ると鼻の機能が落ちるのは普通ですが、中には慢性鼻炎や腫瘍といった病気が隠れていることもあるので注意してください。
加湿器で部屋の湿度を上げたり、水をたくさん飲ませたりすると良いでしょう。もし鼻づまりがなかなか治まらない場合や胃食欲がなくなったり元気がない場合は、早めに動物病院で診てもらうことが大事です。
犬は鼻づまりを起こしているのかチェックする方法

犬の鼻づまりは炎症から感染症、腫瘍まで色々な原因で起こります。症状の重さは原因によって変わるので普段からちょっとした変化に気をつけましょう。特に鼻水の色や粘り気、呼吸音、いびきは体調を知る上で大切です。
ここでは鼻水や呼吸の様子から鼻づまりを見つける方法と病院へ行くべきサインを詳しく説明します。
鼻水の色・粘度を確認
もし透明で水っぽい鼻水なら初期のアレルギー反応か、ちょっとした刺激が原因かもしれません。気温の変化や乾燥も考えられます。大抵は数日で自然に治るでしょう。
しかし、もし黄色や緑色で粘り気のある鼻水が出たら、細菌感染の可能性があります。膿が混じっているなら、炎症が副鼻腔や歯の周りまで広がっているかもしれません。放っておくと長引くこともあるので注意が必要です。
血が混じった鼻水や鼻血が出たら、鼻の中に腫瘍ができているか、ケガをしているか、炎症がひどい可能性があります。出血の色が濃かったり、頻繁に出たりするなら、すぐに動物病院で診てもらいましょう。
早めに気づいて治療することが大切です。
鼻呼吸が困難かどうかのチェック
愛犬の鼻詰まりをチェックするには、鼻先にティッシュをそっと近づけるのが簡単です。普通なら、息に合わせてティッシュが揺れます。しかし鼻が詰まっていると、ほとんど揺れず、呼吸も弱く感じられます。
鼻で息がしづらい犬は、口を開けて呼吸することが多いです。特に寝ている時にいびきをかくのは、鼻詰まりのサインかもしれません。
鼻をよく鳴らしたり、前足で顔をこすったりする仕草にも注意しましょう。
もし呼吸が苦しそうで、舌の色が紫色っぽくなっていたり、急にぐったりしている場合は、すぐに獣医さんに連れて行ってください。放っておくと呼吸困難になることもあります。
普段から愛犬の呼吸音や鼻水の様子をよく見て少しでもおかしいなと思ったら、すぐに対応してあげることが大切です。
こんな症状はない?受診の目安となる症状は?
犬の鼻呼吸が順調かどうかを見るのも鼻づまりを知る上で大事です。「スースー」「ブーブー」と音がしたり、寝ている時のいびきがひどい場合は鼻の通りが悪くなっているかもしれません。
もし以下の症状が見られたら状態がかなり悪いかもしれないので、すぐに病院へ行ってください。
- 呼吸が荒く、口を開けて呼吸している
- 鼻血が止まらない
- 顔が腫れたり、形が変わっている
- 元気や食欲がない
- くしゃみや咳を何度もする
- 鼻水や涙が大量に出る
- 苦しそうにして倒れ込む
こういった症状は、感染症や腫瘍、急な炎症など命に関わる病気のサインかもしれません。大丈夫だろうと放っておかず、すぐに動物病院で診てもらいましょう。
家庭でできる犬の鼻づまり対処法

犬が鼻づまりになった時、原因や状態によって対応が変わります。
たとえばお家でできるケアで一時的に楽にしてあげられます。部屋の湿度を調整したり、蒸しタオルで鼻を温めたり、軽くマッサージしてあげると、呼吸が楽になることが少なくありません。
それから、栄養補助としてサプリメントを使うのも一つの手です。
ここでは、犬が少しでも快適に過ごせるように、家庭でできる簡単で安心なケアの方法を詳しく説明します。
部屋の湿度を上げる
室内が乾燥していると犬の鼻詰まりが悪化しやすくなります。
空気が乾燥すると鼻の粘膜が傷つき炎症で呼吸が苦しくなることがあります。部屋の湿度は50~70%に保つのが良く、加湿器を使うといいでしょう。
もし加湿器がない場合は濡れたタオルを部屋に干したり、水をコップに入れて暖房のそばに置いても同じような加湿ができます。
それからエアコンの風が直接当たらないように犬の寝る場所を考えてあげるのも大切です。特に冬は暖房で空気が乾燥しやすいので、日中と夜で湿度をチェックするようにしましょう。
部屋の湿度を適切に保てば鼻の粘膜が潤って、くしゃみや咳の予防になるので、そのおかげで犬の睡眠や体調も良くなるはずです。
蒸しタオルを使った鼻周りのケア
犬の鼻を温めるには40℃くらいの蒸しタオルを使うのがおすすめです。温めることで血行が良くなり、鼻の通りがスムーズになることが期待できます。
タオルの温度は必ず手で確認し、熱すぎないように注意してください。1回1~2分を目安に1日に数回行うと良いでしょう。温かい蒸気で鼻の中の乾燥が和らぎ鼻水も出しやすくなります。
リラックスできて愛犬の表情が穏やかになることがほとんどです。ただし炎症や腫れがひどい場合は逆効果になることもあるので獣医さんに相談してください。
温めケアは、あくまで補助的なものとして安心できる環境で優しく行ってあげましょう。
ツボ押しマッサージ
犬の鼻詰まりに効くツボとして「山根(さんこん)」という場所があります。
場所は眉間から鼻筋の上あたりです。指の腹で軽く押すと鼻の通りが良くなると言われています。マッサージする時は、力を入れすぎず優しく円を描くようにするのがコツです。
手が冷たいと犬がびっくりするので、先に温めておくと良いでしょう。
また、マッサージで飼い主さんとの触れ合いが増えて、リラックスできる効果も期待できます。もし嫌がるようなら無理に続けず落ち着いた時にまた試してみてください。
日課にすることで呼吸が楽になり鼻詰まりのストレスを減らせます。マッサージが終わったら褒めたりおやつをあげたりして気持ちいい体験として覚えてもらいましょう。
サプリや健康食品の活用
慢性的な鼻づまりに悩む犬には、免疫や粘膜を助けるサプリメントを試すのもいいかもしれません。
例えば、オメガ3脂肪酸は炎症を抑える作用があるので、鼻や気道の炎症を和らげるのに役立つ可能性があります。プロバイオティクス(乳酸菌など)は腸内環境を良くして、全身の免疫バランスを整えます。ビタミンEやビタミンCは、粘膜を健康に保つ手助けをしてくれます。
ただし、サプリメントは薬ではないので、すぐに効くわけではありません。
続けて与えることで体質改善につながることがありますが、与えすぎには注意してください。
与える前には犬の体重や持病を考えて、必ず獣医さんに相談しましょう。バランスの良い食事と一緒にサプリメントを使うことで、犬の健康を内側からサポートできます。
犬の鼻づまり病院での検査・治療

犬が鼻づまりを起こしている場合、軽く考えずに動物病院で診てもらうのが大切です。実は、副鼻腔炎や腫瘍といった深刻な病気が隠れていることがあるからです。
病院では問診やレントゲンなどの検査を通じて原因を特定し、それぞれの犬に合った治療を行います。ここでは病院で行われる主な検査と治療方法を順番に見ていきましょう。
病院での検査内容
①問診と触診を行います
どんな症状がいつから始まったのか生活環境に変わったことはないかなど飼い主さんに詳しくお話をききます。その上で鼻や顔に左右差や腫れがないか、呼吸音がおかしくないかなどを確認する流れです。
② 血液検査
体の炎症反応や感染症がないかを調べます。ウイルスや細菌による感染や免疫の異常がないかどうかも確認します。これは体の状態を把握するためにとても大事な検査です。
③ レントゲン・CT・MRI検査
鼻の中や副鼻腔の様子、骨の状態、腫瘍がないかなどを画像で確認します。CT検査は細かい骨の状態や炎症の広がりを見るのに適しています。MRI検査では腫瘍や炎症の性質について詳しく調べられます。
④ 鼻水の検査(細胞診・細菌培養検査)
鼻水の中にどんな細胞や細菌がいるかを顕微鏡で調べ感染症があるかどうか原因となっている菌は何かを特定します。どの抗生物質が効くかを判断するために重要な検査です。
⑤ 内視鏡検査(鼻鏡検査)
細いカメラを鼻から入れて鼻の中を直接観察します。異物やポリープ、腫瘍、副鼻腔炎の状態などを確認できます。ほとんどのケースで全身麻酔をして安全に行います。
犬の鼻づまりの治療法
① 薬を使う治療
原因に合わせて、抗菌薬、炎症を抑える薬、抗ヒスタミン薬、ステロイドなどを使います。特に、バイ菌が原因の鼻炎やアレルギー性の鼻炎によく効きます。
② 内視鏡を使った手術
鼻の中に入った物や腫瘍を取り除く手術です。早く見つけて取り除けば、症状が早く良くなり、呼吸もしやすくなります。
③ 副鼻腔を洗浄する治療
副鼻腔炎や蓄膿症の場合は、洗浄して膿やドロドロした鼻水を洗い流します。鼻づまりや不快感を軽くするのに、とても役立ちます。
④ 体をサポートする治療(栄養と環境の管理)
体の免疫力を上げるために食事に気をつけたり、アレルギーの原因となる物をできるだけ取り除くなど、環境を良くすることも行います。普段の生活を見直すことが、再び症状が出ないようにするために重要です。
⑤ 放射線治療や薬物療法
もし腫瘍が悪性だった場合は、手術に加えて放射線治療や抗がん剤を使う治療を行います。犬の体力に合わせて治療計画を立てて生活の質をできるだけ維持できるようにします。
犬の鼻づまりに関するよくある質問

いつ治るか、散歩に行っても大丈夫か、鼻が乾いている時のケア、何か良い物はあるかなど気になることは多くあります。
ここでは犬の鼻づまりについて飼い主さんからよくある質問をまとめ、その原因と対処法を分かりやすく説明します。
犬の鼻づまりはどのくらいで治りますか?
軽いアレルギーや風邪なら数日~1週間くらいで自然に治ることも少なくありません。しかし副鼻腔炎や慢性的な鼻炎、腫瘍などが原因だと治療に数ヶ月かかることもあるため注意しましょう。
治療は薬を飲ませたり、ネブライザーで加湿したりしますが、再発することもあります。
完全に治すには焦らずにケアを続け、定期的に獣医さんに診てもらうのが大事です。
犬が鼻づまりのとき散歩をしてもいいですか?
軽い鼻詰まりなら散歩はたいてい大丈夫でしょう。
しかし呼吸が苦しそうだったり咳き込んだりするようなら無理させずに休ませてあげてください。
散歩するなら花粉やほこりが多い場所や車の排気ガスが多い道は避けて空気のきれいな場所で短時間にするのがおすすめです。それと朝晩の寒い時間帯は鼻が刺激を受けやすいので、昼間の暖かい時間を選ぶのもポイントといえます。
体調を見ながら、無理のないペースで散歩することが大事です。
犬の鼻が乾いていて苦しそうです。どうすればいいですか?
犬の鼻が乾燥するとすごく不快で鼻詰まりもひどくなることがあります。
まず加湿器で部屋の湿度を40~60%に保つのがおすすめです。ほかにも蒸しタオルで鼻の周りを軽く温めたり、犬用の保湿スプレーやワセリンを少し塗ってあげると、鼻の乾燥が和らぎます。
ただ、塗りすぎると鼻の穴をふさいだり、舐めてお腹を壊すこともあるので気を付けてください。
もし症状が続くようでしたらアレルギーや感染症の可能性もあるので、早めに獣医さんに診てもらいましょう。
犬の鼻づまりにおすすめのグッズはありますか?
犬の鼻づまりには加湿器やネブライザー(吸入器)が役立ちます。ネブライザーは、薬や水を霧状にして鼻に届けるので鼻の粘膜を潤しつつ炎症を抑えられます。
他にも蒸しタオルや保湿スプレー、ツボ押しグッズも使うと血行が良くなったり、リラックスできたりするでしょう。
免疫力や粘膜の健康を助けるサプリメントも売られていますが成分や安全性はそれぞれ違います。使う前に必ず獣医さんに相談して愛犬に合うものを選んであげてください。
犬の鼻づまりを予防するにはどうすればいいですか?
犬の鼻づまりを防ぐには、まず生活環境をきれいに保つことが大事です。
ホコリや花粉あるいはハウスダストといったアレルギーの原因になるものを減らすために、こまめに掃除して換気をしましょう。
また加湿器や空気清浄機を使って部屋の湿度をちょうどいい状態に保つことも大切です。それから、バランスのいい食事や適度な運動、定期的な健康チェックで免疫力を維持できます。
もし愛犬がアレルギー体質なら獣医さんと相談して、季節や環境に合わせた特別なケアを続けると良いでしょう。
まとめ

犬の鼻づまりはアレルギーから慢性的な炎症、まれに腫瘍など多くの原因が考えられます。毎日鼻水の色や呼吸の状態をよく見て少しでもおかしいなと思ったら、すぐに動物病院で診てもらいましょう。
家では加湿器を使ったり鼻の周りを保湿してあげるのも犬が楽に呼吸できるようにするためには良い方法です。
正しい知識を持って早めに鼻づまりに対応することが愛犬の健康と快適な生活を守るためにとても大切です。


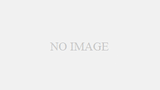
コメント