ペットを亡くした人に何と言えばいいか迷うことは多いはずです。家族のように大事なペットを失った悲しみは本当に大きいことから、かける言葉が見つからないのも当然です。
大切なのは相手の気持ちに寄り添ってペットを亡くした悲しみを否定しないこと。「つらいね」と声をかけて共感したり、楽しかった思い出を話したりするのがいいでしょう。その一方で「また飼えばいいよ」といった軽い言葉は、飼い主さんの不快感を増大させてしまうことから避けるべきです。
そこで今回は友達やペットを亡くした人にかけるために心からのメッセージの例とペットを亡くした際に言わない方が望ましい言葉を詳しくお伝えします。
ペットを亡くした人にかける言葉と基本マナー

ペットロスは家族を失うのと同じくらいつらいものです。長年一緒にいたペットがいなくなる喪失感は、人によっては他の誰かを亡くした時よりも大きく感じられることもあります。
そんな時、飼い主さんにどんな言葉をかけるかよりも、どんな気持ちで伝えるかが重要です。形式的な言葉よりも相手の悲しみに寄り添う気持ちや黙ってそばにいることが心の支えになるからです。
ここでは、ペットを亡くした人にかける言葉として、特に大切な3つのポイントを解説します。
「お悔やみ申し上げます」は使って構わない
ペットロスの方に「お悔やみ申し上げます」と言うのは、丁寧な弔意を示す表現としてOKです。以前は人にしか使わないと考えられていましたが、今はペットを家族と考える人が多いので、心からの「お悔やみ申し上げます」は、むしろ自然で誠実な言い方でしょう。
ただ、「ご冥福をお祈りします」は宗教的な意味合いがあるので、相手の信仰などを考えて使う必要があります。もし迷ったら、「〇〇ちゃんのこと、心よりお悔やみ申し上げます」「お辛いお気持ち、お察しします」のような優しい言葉を選びましょう。
大事なのはペットをただの動物としてではなく、大切な家族を亡くした人として敬意を払うことです。
形よりも気持ちを大切にして相手の悲しみに寄り添うことが大切です。
相手の気持ちを否定しない
ペットロスは人によって感じ方が違うことから、泣いたり、何も言えなくなったりすることは多いはずです。どんな反応も普通のことですし、「弱い」、「いつまでもくよくよしてる」といった言葉使いは望ましくありません。泣いてても落ち込んでても、「つらかったね」「本当に大切な子だったんだね」と気持ちを受け止めることが一番大切です。
無理に元気を出させようとせずに静かに話を聞いてあげるだけで、気持ちの整理にもなります。もし思い出話をしたいようなら「そんなことあったんだ」「幸せだったね」と共感してあげると心が少しずつ癒えていくでしょう。
焦らずに、その人のペースに合わせて一緒に安心できる時間を過ごすことが何よりの優しさです。一番大切なのは相手の気持ちを理解して、安心させることなのです。
軽率な励ましや安易な言葉は避ける
ペットを亡くしたばかりの方には、かける言葉に注意が必要です。想像以上に深い悲しみを抱えている場合があるので「早く元気出して」や「新しいペットを飼ったら?」といった言葉は、かえってつらい思いをさせてしまうことがあります。
悲しみを無理に乗り越えさせようとせず深い愛情の表れとして受け止めることが大切です。一方、慰めたい気持ちが強すぎると相手の気持ちに寄り添えなくなることもあります。亡くなった原因を詮索したり「ああすればよかったのに」といった後悔を誘うようなことは絶対にやめましょう。
相手が話したい時に静かに耳を傾けるのが一番良いのです。「無理しないでね」「いつでも話を聞くよ」といった短い言葉でも、相手の心に響くことがあります。優しい沈黙と静かなまなざしが、悲しみを和らげる手助けになるはずです。
ペットを亡くした人にかける言葉で避けるべきNGワードは?

ペットロスに苦しむ人にどんな言葉をかけるべきか悩むことはあるはずです。こちらで良かれと思って言ったことが実は相手を深く傷つけてしまうことも少なくないからです。
ここでは、相手の気持ちを尊重するために絶対に口にしない方がいい言葉や避けるべき表現について、そして代わりとなる言葉についてもお話しします。
失った命を軽く扱う言葉
「ペットなんて」「寿命が短いのは当然」「動物はいつか死ぬもの」といった言葉は、相手が抱く深い愛情を否定するとても配慮に欠けた言い方です。多くの人がペットを家族のように思い、心の支えとして生きがいを感じています。
そうした存在を軽く扱う言葉は、悲しんでいる人の心を深く傷つけてしまう可能性があります。大切なのは「ペットは家族」という認識を共有し、その存在の大きさを理解することです。
「大切な家族だったんだね」「本当に愛されていたんだね」と共感する言葉こそが相手の心に寄り添う一番良い言葉になるでしょう。
代わりを勧める言葉
「すぐに次の子を迎えれば」とか「また飼えばいい」という言葉は励ましているつもりでもペットを亡くした人には酷に聞こえることがあります。亡くなったペットは唯一無二の存在で、どんな新しい命も代わりにはなれません。悲しんでいる人にそんなことを言うと「あなたの愛情はその程度だったんですね」と捉えられてしまうこともあるのです。
大切なのは新しいペットを飼うことを勧めるのではなく、今はただ悲しみに寄り添うことです。「無理に元気を出さなくていい」「悲しいのは当然だよ」と今の気持ちを受け止める言葉をかけてあげましょう。
責任を追及し罪悪感を強める言葉
「もっと何かできたんじゃないか」「あの時、ああしていれば」といった言葉は、飼い主さんの罪悪感をより強くしてしまうことがあります。ペットを亡くした方は、ご自身を責めていることが多いので周りの人の言葉でさらに傷ついてしまうこともあります。
つらい気持ちに寄りそう時は、原因を尋ねたりするよりも「頑張ったね」「愛情をかけていたね」と伝えることが大切です。「最後まで本当によく頑張ったね」「〇〇ちゃんは幸せだったと思うよ」という言葉は罪悪感を軽くし心を癒してくれるでしょう。
相手のつらさを理解し静かに共感することが何よりも優しい心遣いになります。
相手・関係別!ペットを亡くした人にかける言葉

ペットを亡くされた方にかける言葉は、その方との間柄によってふさわしい言い方や距離感が変わってきます。親しい方には気持ちに寄り添った温かい言葉が大切ですし、仕事関係の方などには、礼儀正しく控えめな言い方が大切です。
ここでは相手との関係性別に、どんな言葉をかけたら良いのか、そのマナーを紹介します。
友人・恋人など親しい間柄
親しい人に弔いの言葉をかける時は形式ばったものではなく、心からの自然な言葉が一番です。「お悔やみ申し上げます」のような堅苦しい言い方より、温かくて優しい言葉を選びましょう。
例えば、「○○がいなくなって私も寂しい。つらいよね」とか「○○は、△△にすごく大切にされて幸せだったね」と言うと相手の悲しみに寄り添う気持ちが伝わるはずです。
無理に元気づけようとするより、「泣いてもいいんだよ」「何か話したくなったら、いつでも聞くからね」と、相手の気持ちを受け止めることが大切です。直接会えるなら言葉で何か言うよりも、ただ静かに話を聞いたり、そばにいたり、そっと肩に手を置いたりするだけでも相手にとって大きな慰めになります。
相手の気持ちを尊重して時には黙って寄り添うことも大切な思いやりです。
職場の同僚や仕事関係の人
職場や取引先では感情的になりすぎず、礼儀正しい言い回しを心がけましょう。メールで伝えるなら「愛犬(愛猫)のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます」「さぞお辛いことと存じます」といった文章が望ましいといえます。
親しい同僚になら、「〇〇ちゃんのことを聞きました。大変だったね」「何かできることがあれば、遠慮なく言ってください」と、控えめに声をかける方が感じもよく伝わります。特に上司や取引先など目上の人に対しては、ペットの名前や病気の詳しい話はせず、シンプルに気持ちを伝えましょう。
もし相手が触れてほしくなさそうなら、無理に話題に出さないのも大切です。職場では相手の気持ちを考えつつ仕事の面でサポートすることで、思いやりを示すのが良いでしょう。
子どもや年配者
お子さんがペットをなくした時は、「もう泣かないで」と言うより「つらいね」「○○は、あなたと一緒で幸せだったと思うよ」と気持ちを言葉にしてあげましょう。悲しむことを否定せず泣くのは当然のことだと受け入れることで命や愛情について学べるはずです。
一方、年配の方がペットをなくした場合は長い間の絆やペットがいた日常がなくなる喪失感が大きいので「長い間一緒で、本当に幸せでしたね」「寂しいのは、それだけ愛していたからですよ」のような言葉が心に届くでしょう。どちらの場合も悲しみをなくそうとするのではなく、気持ちを受け止めて寄り添うことが大事です。
相手の気持ちを尊重し無理に元気づけようとせず、一緒に悲しむことが一番の支えになります。
ペットを亡くした人にかける言葉|状況別の例文

ペットを亡くされた方にかける言葉は、状況によって大きく変わります。病気や老衰、事故など亡くなった原因によって飼い主さんの気持ちは大きく違うものです。
そして、同じ悲しみでも感情の種類や大きさは人それぞれです。まずはその気持ちを理解し、そっと寄り添うことが大切です。ここでは、状況に合わせた言葉選びを紹介します。
病気で亡くなった場合にかける言葉
病気でペットとのお別れは、飼い主さんも長期間の通院や看病で心身ともに疲れていることが多いものです。そんな時は「本当によく頑張ったね」「できる限りのことをしてあげたね」と飼い主さんの努力をねぎらう言葉が心に響きます。
「〇〇ちゃんも、あなたが一緒にいてくれて安心したと思うよ」「最後まで見守ってくれて幸せだったね」のように愛情を込めて努力を認める言葉を選びましょう。時には飼い主さんの話を涙を流しながら聞いてあげることこそが一番の慰めになることもあります。
反対に「もっと早く気づいてあげればよかった」「つらかったね」といった後悔や苦しさを強調する言葉は避けるべきです。病状や治療について詳しく触れず「あなたの気持ちはちゃんと伝わっていたよ」と伝えることで飼い主さんの心を少しずつ癒すことができるでしょう。
事故や突然亡くなった場合にかける言葉
突然のペットとの別れは、飼い主さんにとって大きなショックでしょう。かける言葉によっては、かえってつらい思いをさせてしまうこともあります。まずは「かける言葉が見つからないくらい、つらいですね」「本当に突然で、私も心が痛みます」とストレートに気持ちを伝えるのが大切です。
飼い主さんは「もっと何かできたのでは」と自分を責めてしまいがちなので「〇〇ちゃんは、あなたの愛情をたくさん受けて幸せだったと思いますよ」「きっと、今もあなたのことを見守ってくれていますね」と愛情を伝える言葉は心に響くはずです。
一方で「どうして亡くなったの?」「何かあったの?」などと、理由を聞くのは避けましょう。無理に元気づけようとするよりも、ただそばに寄り添って話を聞いてあげる方が心に残ることもあります。黙って話を聞いたり、うなずいたりするだけでも十分な慰めになります。
長寿での旅立ちの場合にかける言葉
ペットが長生きして亡くなった時は悲しいけれど、感謝や誇らしい気持ち、そして安らかな気持ちが入り混じります。そんな時は「長い間お疲れ様」「たくさんの幸せをありがとう」といった優しい言葉をかけてあげましょう。
それに「〇〇は幸せな一生だったね」「最後まで一緒にいられて本当に良かった」と一緒に過ごした喜びを伝えるのも良い対応です。飼い主さんにとっては、家族の歴史そのものを見送るような気持ちになります。一方で「長生きしたんだからもう十分」「幸せだったでしょ」と無理に悲しみを抑えるような言葉は使わない方が良いでしょう。
悲しみに対しては「一緒に過ごした時間は、きっと宝物になっているよ」と伝えることで悲しみをそっと包み込んであげられます。
メッセージアプリやSNSで役立つ!ペットを亡くした人にかける言葉

ペットを亡くされた方へメッセージを送る際は直接話すより軽く見えがちです。そのため言葉選びは特に大切です。
文章の長さや言い回し、絵文字の使い方で相手の気持ちを大きく左右する可能性もあります。だからこそ、短い文章でも心が伝わるように、そして返信を求めない姿勢で送ることが重要です。ここでは、スマホでも優しさと誠実さが伝わるメッセージの書き方をご紹介します。
短くても気持ちが伝わる文章に
メッセージを送る際は、長々とした文章よりも短く気持ちが伝わる言葉を選びましょう。例えば「○○ちゃんのことを知って、すごく心が痛みました。今はゆっくり休んでね」や「○○ちゃん、本当に幸せだったね。どうか体を大切にしてね」のように相手を気遣うシンプルなメッセージがおすすめです。
もしペットの名前を知っている間柄なら、ペットの名前を出すと「ちゃんと分かってくれているんだな」と感じてもらいやすいでしょう。特別な存在として尊重する気持ちが伝わるはずです。さらに具体的な思い出を短い一文で加えると、より温かみが増します。例えば「散歩の時によく会った○○ちゃんの笑顔、今でも覚えてるよ」といった感じです。
一方で絵文字やスタンプは親しい間柄でも使いすぎない方がいいでしょう。相手が使ってきた際、同じように使うくらいが安心です。
返信を気にしないこと
悲しいことがあった人にメッセージを送る際「返信は不要です」「読んでいただければ十分です」といった言葉を添えると相手に気を遣わせず、あなたの気持ちを伝えることができます。
メッセージを送る目的は無理に会話を続けることではなく、あなたの気持ちを伝えることです。すぐに返信がなくても、あなたの優しい言葉はきっと相手の心に届くはずです。また、落ち着いた頃に相手から感謝の言葉が返ってくることもあります。焦らず返信を待つことが大切です。一方で何度もメッセージを送ったり、返信を催促したりするのは避けましょう。
相手の気持ちを尊重し、そっと寄り添う気持ちでメッセージを送ることが大切です。
顔を合わせないからこそ避けるべき言葉は?
SNSやLINEでは声や表情が見えない分、軽い気持ちで励ましたり、誤解されるような言い方は避けましょう。例えば、「元気出して!」や「もう落ち着いた?」といった言葉は相手に「早く元気にならなきゃ」とプレッシャーをかけるかもしれません。また「かわいそう」や「次の子を迎えればいいじゃない」と伝えてしまった場合は相手の気持ちを軽く見ているように伝わり、深く傷つけてしまうこともあります。
それから「天国で見守っているよ」のような宗教的な話は人によって受け取り方が違うので気をつけた方がいいでしょう。「いつも心の中で思っているよ」や「思い出はきっと力になるよ」といった誰にでも響く優しい言葉を選ぶのがおすすめです。
直接会えないからこそ、言葉選びは慎重に温かい気持ちを込めることが大切です。
ペットを亡くした人にはかける言葉に関するよくある質問

深い悲しみに暮れている人に、どんな言葉をかければいいか悩むことがほとんどです。実際にかける言葉によっては、かえってつらい思いをさせてしまうこともあります。
ここでは、よくある疑問に答えながら相手の気持ちに寄り添った言葉選びのヒントを紹介します。焦らず、その人のペースに合わせて、そっと支えてあげましょう。
ペットを亡くした直後、どのくらいの期間は連絡を控えるべきですか?
訃報に接した直後は、すぐにご連絡するよりも少し時間を置くのが良いかもしれません。ご遺族の気持ちがまだ落ち着かないうちにお声がけすると、かえってつらい思いをさせてしまったり返信を気にさせてしまったりすることがあるからです。
そのため葬儀後、数日経ってから1週間後くらいに連絡するのが一般的です。ただ、もしご本人から直接ご連絡があった場合は、すぐに一言だけでもお悔やみを述べるのが礼儀です。
また、返信がなくても「読んでくれただけで十分」と考え、何度もメッセージを送ったり、返事を催促するのは控えましょう。今は静かに寄り添うことが大切です。返信がない場合も、そっとしておくのが思いやりだと心得ましょう。
どんな言葉なら相手が心を開きやすくなるのでしょうか?
相手に心を開いてもらうには、ただ励ますだけでなく相手の気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。例えば「つらかったね」「寂しかったね」「○○ちゃんのことを本当に大切に思っていたんだね」といった短い言葉でも気持ちに寄り添う言葉は、相手に安心感を与えます。
「元気を出して」とか「もう落ち着いた?」といった言葉は、相手に立ち直りを急かしてしまうので避けた方が良いでしょう。形式的な弔辞や決まりきった文章よりも自然で温かい言葉を使う方が「この人は分かってくれている」と相手に感じてもらいやすいです。
一番大事なのは、黙ってしまうことを恐れずに相手の気持ちをありのまま受け止めることです。
ペットロスが長引くようなら、どう支援すれば良いですか?
悲しみを乗り越えるまでの時間は人それぞれで数ヶ月から数年かかることもあります。無理に励ますよりも「いつでも話を聞くよ」「無理しないでね」と相手の気持ちに寄り添う姿勢を見せることが大切です。
もし相手が孤立しているように感じたらペットロス専門のカウンセラーや相談窓口を教えてあげるのも良いでしょう。また、食事や家事などを手伝ったり、近所を軽く散歩に誘うなど生活面でサポートすることも大きな支えになります。
時には一緒に思い出を語ったり、写真を見たりする時間を持つことが心を癒すきっかけになることもあります。
メッセージを送った後、相手とどのように接したら良いですか?
メッセージを送った後は相手の気持ちを尊重した接し方を心がけましょう。すぐに励ましたり、相手が触れてほしくないペットの話を持ち出すのは避けるのが賢明です。
返信がなくても焦らずに相手から連絡があるまで待ち、話しかけられたら優しく応じましょう。そうすることで、相手との信頼関係が深まります。「いつでも話を聞くよ」と伝え、静かに寄り添う姿勢を続けることが大切です。
そして日々のちょっとした話題を共有しながら、相手の気持ちが少しでも和らぐような機会を作ってみるのも良いかもしれません。
ペットの死を話題にしても良いタイミングはいつ頃ですか?
悲しみが癒える時期は人それぞれなので「何日後」と具体的に決めることはできません。目安としては1か月ほど経って相手からペットの思い出を話し始めたり、笑顔が見られるようになった頃が良いでしょう。ペットの命日前後や写真を整理し始めたタイミングも話しかけやすいかもしれません。
ただ、一番大切なのは相手の気持ちに寄り添い、相手のペースに合わせて静かに話を聞くことです。例えば「〇〇ちゃん(ペットの名前)の写真、すごく良い顔してるね」といった自然な言葉から会話を始めると相手も話しやすいでしょう。
まとめ

ペットロスの方にかける言葉で大事なのは、何を伝えるかよりもタイミングと寄り添い方です。悲しみの癒え方は人それぞれ。焦らせたり、無理強いしたりせず、ただそばにいることが一番の支えになります。心からの黙とう、共感の言葉、優しい気づかい。そういった小さな積み重ねが孤独から救い出す力になるでしょう。言葉も大切ですが、行動で示すのも大切です。
お花を供えたり、そっと写真を飾ったり、思い出を聞いてあげたりといった優しさが悲しみを癒す光になるはずです。



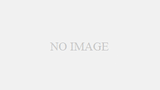
コメント