犬の涙やけの原因には、目の構造や体質、環境など複数の要素が関係します。特に子犬や老犬は涙の量が変わりやすく、ちょっとした刺激でも症状が進むことがあるため注意が必要です。
日常的に見られる症状でも、放置すると皮膚の赤みやかゆみが悪化し、感染を招くこともあります。一方で、早めに原因を特定してあげることで、負担の少ないケアで改善を目指せます。ただし、アレルギーや鼻涙管のトラブルなど、専門的な治療が必要となるケースでは早期受診が重要です。
この記事では、代表的な要因から犬種別の特徴、予防法まで幅広く解説し、愛犬の快適な生活を守るためのヒントを紹介します。
犬に涙やけができる原因

犬の涙やけには、見た目が悪くなるだけではなく、体の不調や隠れた病気が関わっている場合もあります。
ここでは、涙やけが発生する代表的な原因を取り上げ、どのような仕組みで症状が出てくるのかについて分かりやすく説明していきます。
鼻涙管閉塞などの病気
犬の涙は通常、目頭から鼻へ向かう細い管「鼻涙管(びるいかん)」を通って外へ排出されます。
しかし、この通路が生まれつき細かったり、途中でふさがる「鼻涙管閉塞(びるいかんへいそく/鼻と眼をつなぐ涙の通り道が塞がれた状態)」 が起きると、涙が適切に流れず目の周りに溜まってしまいます。その結果、毛に染み込みやすくなり、涙やけとして色が残ってしまいます。
また、犬種によっては顔の骨格や構造の影響で鼻涙管がもともと細い場合もあり、涙が残りやすい傾向があります。
さらに、炎症やケガ、ホコリ・小さなゴミなどの異物が入り込むことで鼻涙管が腫れ、流れが悪くなるケースも見られます。この状態を放置すると涙の量が増えやすく、皮膚のトラブルにつながることがあります。違和感が続く場合は、早めに獣医へ相談することが大切です。
アレルギーや炎症
ハウスダスト、花粉、特定の食材などに対するアレルギー反応は、目の粘膜を刺激しやすく、炎症が起きることで涙の分泌量が増える原因になります。
とくに季節の変わり目は環境が変化しやすいため、アレルギーがある犬にとって結膜炎を起こしやすい時期になります。かゆみが伴うと前足で目をこする回数が増え、さらに刺激が加わることで涙やけが悪化することもあります。
また、室内のホコリやタバコの煙、掃除が行き届かない場所も炎症を長引かせる原因となる可能性があります。
こまめな掃除や空気環境の改善に加え、食事内容の見直しや獣医のアドバイスに基づいたアレルギー対策を取り入れることで、涙の増加を抑えやすくなります。
外部刺激や環境の影響
犬は日常生活の中で、煙やホコリ、強すぎるエアコンの風、掃除に使う洗剤や部屋の芳香剤など、さまざまな刺激を受けています。こうした外部刺激は目の粘膜を乾燥させたり炎症を引き起こしたりしやすく、その結果として涙が増え、涙やけの原因となることがあります。
さらに、室内が十分に清潔でないと、舞い上がったホコリが目に入りやすくなり、毛についた汚れが涙を吸収して毛の変色を進めてしまうこともあります。
さらに、顔周りの毛が長いままでは涙が毛に残りやすく、湿気がこもることで皮膚トラブルにつながる場合もあります。
環境が原因の涙やけは、家庭内の工夫で改善されることがあるため、換気やこまめに掃除、被毛を定期的に手入れするなど、日頃からの予防的なケアが重要になります。
涙やけの原因は犬種も関係!涙やけしやすい犬種とは?
犬の涙やけは体質だけではなく、犬種ごとの顔のつくりや鼻涙管の形状が深く影響しています。特に、骨格的に涙が停滞しやすい犬種では、日常的に涙やけが目立ちやすくなります。
ここでは、涙が残りやすい犬種の特性と、その理由について分かりやすく整理して紹介します。
鼻涙管が狭い犬種
トイ・プードル、チワワ、マルチーズ、ポメラニアン、ヨークシャーテリアなどの小型犬は、涙を鼻へ流す鼻涙管が生まれつき細い場合が多く、涙がうまく排出されにくいという特徴があります。
排出されなかった涙は目元にたまりやすく、結果として涙やけが起こりやすくなります。また、これらの犬種では鼻涙管閉塞が先天的に見られるケースもあり、遺伝的な要素が背景にあるとされています。
幼い頃から涙が多い子も珍しくなく、成長に伴い落ち着くこともありますが、慢性的に続く場合もあります。こまめに目元の状態を観察し、涙が増える時期が長引くときは、早めに病院で確認してもらうことが重要です。
犬種特有の体のつくりを理解しながらケアを続けることで、症状の緩和につながります。
短頭種(たんとうしゅ)
ブルドッグ、フレンチブルドッグ、パグ、シーズー、ペキニーズなどの短頭種は、短くつぶれたような鼻の形状が特徴です。この顔立ちにより鼻涙管が曲がりやすかったり、もともと管が狭かったりするため、涙の排出がスムーズに行われにくい傾向があります。
また、目が前に突き出ている犬が多く、風やホコリといった刺激を受けやすいため、涙がこぼれやすい点も涙やけにつながってしまいます。
さらに、目の周りの皮膚がたるんでいる犬では、しわの部分に汚れがたまりやすく、それが炎症の原因になることもあります。こうした複数の要素が重なり、短頭種では涙やけが悪化しやすくなるため、目元のケアや周囲の清潔を保つことが欠かせません。
涙が多いと感じる時は、早めに獣医へ相談してあげてください。
犬の涙やけを放置すると起こるリスク

涙やけを放置すると、見た目の変色だけでなく、愛犬の健康に影響する可能性があります。ここでは、涙やけをそのままにした場合に起こりやすいトラブルや悪化の要因を取り上げ、注意すべきポイントを解説します。
皮膚の色素沈着・炎症の悪化
涙やけは、涙に含まれる鉄分由来の色素「ポルフィリン」が酸化することで赤褐色に変色し、目の下の被毛や皮膚に色素沈着を起こします。一度濃く染まった箇所はなかなか元に戻りにくく、放置するほど目立ちやすくなる点も注意が必要です。
さらに、涙が常に皮膚へ浸透し続けることで、目元は湿った状態になり、炎症が起きやすくなります。この湿気と刺激が繰り返されると、皮膚が分厚くなったり、赤みやかゆみが強く出たりすることもあります。
その結果、犬が前足で頻繁にこするようになり、傷ができて細菌が入り込み、さらなる悪化を招くケースも少なくありません。
早めのケアを心がけることで、皮膚トラブルを大きく減らすことができます。
細菌やカビの増殖による感染症
目の周りが常に湿った状態にあると、細菌やカビが繁殖しやすくなり、皮膚炎や二次感染を引き起こす原因になります。清潔にしているつもりでも、涙が連続して流れ続ける環境では雑菌が増えやすく、悪化すると独特の臭いがしたり、膿がでることもあります。
こうした感染症は犬にとって強い不快感や痛みの原因となり、かゆみから足でこする行動が増えることで、さらに皮膚が傷つき、症状が悪循環しやすくなります。特に毛が長い犬種では湿気がこもりやすいため、より注意が必要です。
対策としては、日常的に目元を乾かし、清潔を保つケアを続けることで感染のリスクを大きく減らせます。異常が続く場合は早めに動物病院へ相談することが重要です。
目の病気やさらなるトラブルへの悪化
涙やけの原因となる鼻涙管閉塞(びるいかんへいそく)や、まつ毛が内側へ向かって生える眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)を放置すると、角膜炎や角膜潰瘍(かくまくかいよう)、緑内障(りょくないしょう)といった深刻な目の病気へ進行する危険があります。角膜は刺激に弱く、涙が過剰に分泌される状態が続くと傷つきやすく、痛みや不快感が強くなることもあります。
症状が進むと視界がかすむ、光をまぶしがるなどの変化が見られ、そのまま悪化すれば視覚障害につながることもあるので注意が必要です。
さらに、目をこする行動が増えることで角膜の傷が深くなり、治療に時間がかかることも少なくありません。こうした悪循環を避けるためにも、早期の診断と適切な治療が非常に重要です。
犬の涙やけの対策・予防
犬の涙やけは見た目だけでなく健康面にも影響するため、日常的なケアや環境の見直しが欠かせません。ここでは、目元ケアの基本や鼻涙管マッサージ、環境整備、ストレス軽減など、予防につながるポイントを詳しく解説します。
日常の目元ケア
涙やけ対策の基本は、目の周りを常に清潔に保つことです。
涙が残ったままだと汚れが付着しやすく、皮膚トラブルの原因にもなるため、1日に1〜2回を目安に柔らかいガーゼやコットンなどで優しく拭き取ってあげましょう。ぬるま湯や刺激の少ない涙やけ専用クリーナーを使うと、デリケートな目元への負担を抑えながら汚れを落とせます。
また、毛が長い犬は涙が毛に溜まりやすく、湿気がこもって炎症を招きやすい傾向があります。トリミングで目元を短く整えるだけでも、涙の吸収を防ぎ、ケアがしやすくなります。
日々の小さな習慣を積み重ねることで、涙やけの悪化を防ぎやすくなるため、こまめなケアを心掛けることが大切です。
鼻涙管マッサージ
鼻涙管(びるいかん)の流れを促すためには、目の周囲をやさしく温めてあげるケアが有効です。温めたタオルを軽く当てると血行が良くなり、詰まりかけた鼻涙管がほぐれやすくなります。
その後、目をそっと閉じさせ、目頭から鼻の方向へ向かって指の腹でやさしくマッサージすると、涙の排出がスムーズになり、涙やけの進行を抑える効果があります。力を入れすぎると逆に刺激となるため、心地よい程度の弱い圧で繰り返すことが大切です。
また、このケアは涙の流れを整えるだけでなく、目の乾燥予防にもつながり、違和感の軽減にも役立ちます。毎日のケアに取り入れることで、涙が溜まりにくい状態を保ちやすくなります。
環境改善
涙やけを予防するためには、まず室内環境を整えることが欠かせません。ハウスダストや花粉、タバコの煙などは目の粘膜を刺激しやすく、炎症や涙の増加を引き起こす原因となります。こまめな掃除でホコリを減らし、空気清浄機を活用することで、アレルギー要因を大きく抑えられます。
また、部屋の湿度管理も重要です。乾燥しすぎた空気は目の潤いを奪い、涙の過剰分泌を招きやすくなります。逆に湿度が高すぎるとカビや雑菌の繁殖につながるため、適度な湿度を保つことが大切です。
エアコン使用時は加湿器を併用するなど、季節に応じて調整すると負担を減らせます。環境を整える習慣を続けることで、涙の量が安定し、涙やけを防ぎやすい環境づくりができます。
ストレス軽減を意識した生活
ストレスは免疫力の低下を招き、涙やけを悪化させる要因となることがあります。環境の変化や運動不足、飼い主さんとのコミュニケーション不足など、日常の小さなストレスが積み重なることで体のバランスが乱れ、涙の量が増えるケースもあります。
適度な運動をしてあげ、散歩や遊びを通じて心身のリフレッシュを促すことは、ストレス軽減につながります。
また、飼い主さんと触れ合う時間を増やすことで安心感が生まれ、過度な緊張が和らぎやすくなります。
さらに、老廃物の排出をスムーズにするためには十分な水分補給も欠かせません。新鮮な水をいつでも飲めるようにしておくことで、体の巡りが整い、涙やけの改善につながりやすくなります。生活全体を見直し、無理のない習慣を続けることが大切です。
犬の涙やけが悪化している時は動物病院へ

涙やけが急に悪化したり、普段と違う目の症状が見られる場合は、早めに動物病院での診察が必要です。ここでは、受診を判断するためのチェックポイントを紹介します。
痛がる、目をこするなど異常行動がある
犬が頻繁に目をこすったり、痛がって触られるのを嫌がる様子がある場合は注意が必要です。しきりに目を気にする仕草が続くとき、角膜潰瘍(かくまくかいよう)や結膜炎、眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)などの深刻な目のトラブルが隠れている可能性があります。
これらの疾患は進行が早いことも多く、放置すると炎症が広がったり視力に影響が出たりする恐れがあります。
また、目をこすり続けることで角膜に傷がつき、症状がさらに悪化するケースも少なくありません。痛みや違和感は犬にとって強いストレスになるため、早めの対応が重要です。
異変を感じた時点で速やかに動物病院を受診し、原因を特定したうえで適切な治療を進めるようにしましょう。
目ヤニや充血がひどい場合
普段より目ヤニが急に増えたり、粘り気が強くなる場合は注意が必要です。特に黄色や緑色が混じった目ヤニが出ているときは、細菌感染が起きている可能性が高く、早めの医療介入が求められます。
また、目が赤く充血している状態は炎症のサインで、結膜炎や角膜の異常が進行しているケースもあります。
これらの症状は自然に治ることが少なく、放置すると悪化して痛みが強まったり、視力に影響が出る場合もあります。自宅でのケアだけでは十分な改善が難しいため、専門の抗菌薬や抗炎症薬など、獣医による適切な治療が必要です。
目の状態に異変を感じたら、早めに受診し原因を確認することが愛犬の負担軽減のためにも大切です。
涙やけが急に悪化した時
普段は軽い涙やけだったのに、急に範囲が広がったり、こまめに拭いても改善しない状況が続く場合は、何らかの異常が進行している可能性があります。
鼻涙管閉塞(びるいかんへいそく)の悪化や、まつ毛が内側に入り込む眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)の進行、さらにアレルギー反応や細菌感染が悪化しているケースも考えられます。
これらは自然に治ることが少なく、放置すると炎症が広がったり、痛みや視覚への影響が出るおそれがあります。急激な変化は体からのサインでもあるため、早急に動物病院で診察を受け、原因を突き止めたうえで適切な処置を行うことが大切です。
愛犬の負担を少しでも減らすためにも、異変に気づいた段階で早めに対応しましょう。
犬の涙やけに関するよくある質問
犬の涙やけには、日常ケアから病気の可能性まで、さまざまな疑問がつきものです。ここでは、飼い主さんが特に気になりやすい質問を取り上げ、原因や対策について分かりやすく答えていきます。
涙やけのケアで、水道水で目の周りを拭いても良いですか?
涙やけのケアには、水道水ではなく犬用の目元クリーナーやホウ酸水など、殺菌・消毒作用のある専用のケア用品を使うことがおすすめです。水道水は塩素成分が刺激となったり、雑菌が混入する可能性があるため、デリケートな目元には不向きです。
安全にケアするためにも、目の周りの皮膚に負担をかけない専用品を選ぶことが大切です。
食事やドッグフードを変えることで、涙やけは改善しますか?
食事に含まれる特定のタンパク質や添加物がアレルギーを引き起こし、涙の過剰分泌につながることがあります。グレインフリー(穀物不使用)のフードや別のタンパク源へ切り替えることで、アレルギー反応が軽減し、涙やけが改善することもあります。
ただし効果には個体差があるため、自己判断で変更せず、獣医に相談しながら進めることがおすすめです。
涙やけの対策として、サプリメントは効果がありますか?
涙やけ対策用サプリメントには、腸内環境を整える乳酸菌や、オメガ3脂肪酸・アスタキサンチンなどの抗炎症成分が含まれるものがあります。体の内側から炎症やアレルギー反応を抑えるサポートとして利用されますが、単独では十分な改善が難しいこともあります。
獣医に相談し日常のケアや食事管理と併用することで、より高い効果が期待できます。
涙やけのケアで使うコットンやティッシュは、どんなものがおすすめですか?
目の周りはとてもデリケートなため、摩擦を抑えたケアが必要です。毛羽立ちにくいコットンパッドや医療用の滅菌ガーゼ、犬の目元専用ウェットティッシュなど、刺激の少ない素材を選んでください。
ゴシゴシこすらず、優しく押さえるように拭き取れるタイプがおすすめです。
涙やけで変色した毛の色を、元に戻すことはできますか?
涙やけで赤茶色に変色した毛は、すでに色素沈着が起きているため、ケア用品で元々の色に戻すことはできません。まずは目元を清潔に保ち、炎症が落ち着いてからトリミングで少しずつカットしていく方法が基本です。
新しく生えてくる毛をきれいに保つためには、日々のケアを続ける根気強さが大切になります。
まとめ
犬の涙やけは、病気やアレルギー、体質、環境といった複数の要因が重なって起こります。見た目だけの問題と思って放置すると、皮膚炎や感染症へ悪化する可能性があるため注意が必要です。
対策の基本は、毎日の丁寧な目元ケアや鼻涙管マッサージに加え、ストレスの少ない生活環境を整えることです。
ホームケアで良くならない場合や、痛み・充血・急な悪化があるときは、早めに動物病院を受診し、根本的な原因を確認してください。飼い主さんの根気強い継続的なケアで、愛犬が快適に過ごせる環境を整えてあげてくださいね。



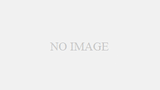
コメント