老犬が暑くもないのにハァハァと息を荒くするのは、実はさまざまな理由が隠れていることがあります。
犬は本来、体温を下げるために呼吸を早めますが、気温が高くない状況でも続くようなら注意が必要です。年齢に伴う体力の衰えや呼吸器の機能低下、心臓や肺の病気、さらには痛みや不安・緊張といったストレス反応が関係している場合もあります。
この記事では、老犬が暑くないのにハァハァする原因を整理し、考えられる病気や対処法、そして受診の目安をわかりやすく解説します。日々の呼吸の変化を見逃さず、早めに異変に気づくことが、愛犬の健やかな生活を守る秘訣になります。
老犬が暑くないのにハァハァする理由とは?

老犬が暑くないのにハァハァしているとき、その原因は一つではありません。ストレスや軽い運動による息切れ、体温調節の反応、一時的な体調不良、そして加齢による呼吸機能の低下など、さまざまな要因が関係しています。
ここでは、それぞれの理由を詳しく解説します。
緊張やストレスによる呼吸の乱れ
犬は強い不安や緊張、恐怖を感じると、交感神経が活発になり心拍数や呼吸数が上昇します。その結果、気温に関係なく「ハァハァ」と荒い呼吸を繰り返すことがあります。
特に老犬は加齢によってストレスへの耐性が下がり、わずかな環境の変化にも敏感に反応する傾向があります。引っ越しや騒音、来客、飼い主さんの不在など、普段とは違う出来事が刺激となり、呼吸の乱れが起こりやすくなります。
また、慢性的な不安が続くと自律神経のバランスが崩れ、呼吸だけでなく消化機能や免疫力の低下にもつながることがあります。老犬が落ち着ける静かな環境を整え、安心できる空間で過ごせるよう環境づくりが大切です。
運動によって起こる息切れ
散歩や遊びのあとに老犬がハァハァと呼吸を荒くするのは、体内に酸素を取り込み、筋肉にたまった乳酸を処理するための正常な生理反応です。しかし、加齢によって筋肉量や心肺機能が低下すると、軽い運動でも呼吸が整うまでに時間がかかることがあります。
若い頃はすぐに落ち着いていたのに、最近は息切れが長引くといった変化が見られる場合は注意が必要です。
特に肥満傾向の犬や、僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう:心臓の弁がきちんと閉じず血液が逆流する病気)などの心臓疾患、気管虚脱(きかんきょだつ:気管が押しつぶされて空気の通り道が狭くなる病気)を抱える犬では、運動後に呼吸が苦しそうに見えることもあります。
単なる疲れだと判断せず、呼吸の速さや持続時間を観察し、異常が続く場合は早めに受診することが大切です。
体温調節
犬は人間のように汗で体温を下げることがほとんどできず、主に舌や口腔、呼吸を通じて気化熱を発生させることで体温を調節しています。この仕組みが、いわゆる「パンティング」と呼ばれるハァハァとした呼吸です。
飼い主さんが「暑くない」と感じていても、犬にとっては室温や日差し、湿度、被毛の厚さなどが原因で体温が上昇している場合があります。特に老犬は体温調節機能が衰えやすく、わずかな気温差や軽い運動でもパンティングを起こすことがあります。
また、夏場だけでなく、春や秋、冬でも注意が必要です。暖房の使い過ぎや犬の服の着させすぎが原因で体温が上がることもあるため、季節を問わず室温や湿度の管理を意識しましょう。
加齢による呼吸機能の低下
老犬になると、呼吸に関わる横隔膜や肋間筋といった筋肉が少しずつ衰え、肺の弾力性も低下します。これにより深くゆっくりした呼吸が難しくなり、酸素を効率よく取り込む力が落ちてしまいます。
その結果、軽い動作でも息が速くなり、「ハァハァ」と呼吸が荒くなることがあります。
筋肉の衰えは呼吸運動を支える力を弱め、肺の弾力性低下は空気の出入りをスムーズに行えなくするため、老犬ほど呼吸の効率が下がります。これらは加齢に伴う自然な変化であり、特に運動後や興奮時には症状が目立ちやすくなります。
老犬が暑くないのにハァハァするときに疑うべき病気

老犬になると、呼吸に関わる筋肉である横隔膜(おうかくまく)や肋間筋(ろっかんきん)の力が徐々に弱まり、肺の弾力性も低下していきます。筋力低下は、深くてゆっくりとした呼吸が難しくなり、効率的に酸素を取り込む力が衰えてしまいます。
その結果、散歩や体の向きを変えるなどの軽い動作でも息が速くなり、「ハァハァ」と呼吸が荒くなりやすくなります。
また、筋力の衰えは呼吸運動を支える力を奪い、肺の弾力性低下は空気を出し入れする柔軟性も衰えるため、呼吸自体の効率がさらに落ちます。こうした変化は加齢に伴う自然な生理現象であり、特に運動後や軽い興奮時によく見られます。
全身の筋力低下や体力の減少も関係しており、呼吸が浅く速くなる傾向は老犬では避けられない原因の一つです。
肺炎
肺炎は、気管支や肺に炎症が起こる病気で、咳や呼吸困難、発熱、食欲や元気の低下などが見られます。呼吸の際にゼーゼーや、ヒューヒューといった異音が聞こえることも多く、重症化すると舌や歯茎の血色が悪く、青紫色に変わっている状態(チアノーゼ)になり、意識がもうろうとすることもあります。
老犬は体力や免疫力が低下しているため、細菌やウイルス、誤嚥(ごえん)などが原因で肺炎を発症しやすく、進行が早いのが特徴です。放置すると命に関わる危険もあるため、咳が続く、呼吸が荒い、元気がないなどの症状が見られた場合は早急に受診することが大切です。
早期発見・治療により回復の見込みが高まるため、日常的な呼吸の変化にも注意を払いましょう。
気管虚脱
気管虚脱(きかんきょだつ)は、気管を支える軟骨が変形して弱くなり、気管が押しつぶされることで空気の通り道が狭くなる病気です。呼吸がしづらくなり、ガーガーというガチョウの鳴き声のような咳が続くのが特徴です。
興奮時や運動後には息苦しさが増し、パンティング(口を開けてハァハァと呼吸する行動)や呼吸困難、チアノーゼ(舌や歯茎の血色が悪く、青紫色に変わっている状態)が見られることもあります。
特に小型犬や高齢犬に多く発症し、肥満や首輪による圧迫、慢性的な咳が悪化要因となることがあります。進行すると酸素不足を起こし命に関わる危険もあるため、呼吸音が荒い、咳が長引くなどの症状がある場合は早めに動物病院を受診してください。
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症/ふくじんひしつきのうこうしんしょう)は、副腎から分泌される「コルチゾール」というホルモンが過剰に出ることで起こる病気です。多飲多尿(たくさん飲んでたくさん排泄すること)、食欲の異常な増加、腹部のふくらみ、皮膚の乾燥や毛の脱落、筋力低下などが主な症状として見られます。
また、呼吸が浅く速くなる「パンティング」も特徴の一つで、暑くないのに口を開けてハァハァしている場合には注意が必要です。進行すると免疫力の低下や糖尿病の併発などを引き起こすこともあります。老犬に多い病気のため、行動や見た目の変化が見られたときは早めに動物病院で血液検査などを受けることをおすすめします。
僧帽弁閉鎖不全症
僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)は、心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁がしっかり閉じなくなり、血液が逆流してしまう病気です。
初期には目立った症状が少ないものの、進行すると疲れやすくなったり、動きたがらない、咳が出る、食欲が落ちるといった変化が見られます。さらに悪化すると、呼吸困難や腹部の膨らみ、失神などが起こることもあります。
重症化すると肺水腫を併発し、ゼーゼー・ハァハァといった荒い呼吸やチアノーゼ(舌や歯茎の血色が悪く、青紫色に変わっている状態)が現れる場合があります。老犬に多い心臓病の一つであり、早期発見と内服治療の継続が非常に重要です。少しでも呼吸が苦しそうに見えるときは、すぐに動物病院を受診しましょう。
鼻炎や気管支炎
鼻炎や気管支炎は、鼻汁やくしゃみ、咳、鼻づまり、呼吸困難、疲れやすさなどが代表的な症状です。鼻炎はウイルスや細菌、ハウスダストなどが原因で起こり、慢性化すると粘膜の炎症が広がり、呼吸がしづらくなることがあります。気管支炎では、気管や気管支に炎症が起き、ゼーゼーとした呼吸音や咳が続くのが特徴です。
特に老犬は免疫力が低下しているため、これらの炎症が長引きやすく、重症化すると呼吸困難や顔面の腫れ、変形が見られることもあります。呼吸が荒い、鼻が詰まって苦しそうと感じたら、早めに動物病院を受診することが大切です。
治療とあわせて、空気の乾燥を防ぐ・室内を清潔に保つなどの環境作りを行うことで、症状の改善につながります。
老犬が呼吸異常を見極めるチェックポイント

老犬の呼吸異常は命に関わることもあり、正常な呼吸かどうかを見極めることは飼い主さんの大切な役割です。高齢になるほど呼吸器や循環器の疾患リスクが高まるため、日々の観察で早めに異変を見つけ、適切に対応することが重要です。
ここでは老犬の息が荒いときに確認したいチェックポイントを紹介します。
正常な呼吸数であるか確認する
犬が寝ているときやリラックスしているときの安静時の正常な呼吸数は、1分間におよそ10〜35回が目安とされています。高齢犬や犬種、体格によって多少の差はありますが、涼しい環境下で40回を超えるような早い呼吸が続く場合は注意が必要です。呼吸数の増加は、呼吸器や心臓の異常、体調不良のサインであることもあります。
呼吸数を測る際は、愛犬が落ち着いているタイミングで胸やお腹の動きを観察し、10秒間または15秒間の回数を数えます。その数をそれぞれ6倍・4倍して1分あたりの呼吸数を算出しましょう。
日常的にチェックしておくと、異変の早期発見につながります。特に老犬では小さな変化が大きな体調のサインとなるため、記録をつけて経過を観察することもおすすめです。
呼吸の速さ・浅さ、異音がないか
老犬の呼吸異常を見極めるポイントには、普段より呼吸が速くなっていたり、浅い呼吸をしていることがあります。胸やお腹が大きく動く浅い呼吸や、ヒューヒュー、ガーガーといった異音を伴う場合は要注意です。これらは呼吸器や心臓に負担がかかっているサインであることが多いです。
また、咳が続く、上を向いて呼吸している、伏せた姿勢を取れない、夜に落ち着いて眠れないなどの様子も見逃せません。さらに、舌や歯茎などの粘膜が白っぽい、あるいは紫色になっている場合は、血液中の酸素が不足している可能性があり危険です。こうした症状が見られるときは、呼吸困難や循環器疾患のリスクが高いため、早急に動物病院を受診するようにしましょう。
舌の色が青や紫になっていないか
健康な犬の舌は濃いピンク色からやや赤みを帯びており、血液や酸素の循環が正常に行われている状態を示します。これに対し、舌が青や紫色に変化している場合は「チアノーゼ」と呼ばれ、血液中の酸素が著しく不足している危険な状態です。
チアノーゼは、呼吸器や循環器の異常、気道の閉塞(へいそく)などによって十分な酸素が体内に取り込めなくなっているサインです。特に心臓病や肺の疾患が進行している犬に多く見られ、放置すると呼吸困難や意識障害に発展し、命に関わる場合もあります。
舌や歯茎の色が普段より暗い、紫がかって見える場合は、迷わず動物病院を受診してください。早急な酸素吸入や精密検査が必要となるケースもあり、飼い主さんの迅速な対応が命を守る鍵となります。
老犬が暑くないのにハァハァしているときの対処法

老犬が暑くないのにハァハァと呼吸しているとき、「落ち着かないのかな」「苦しいのかな」と感じる飼い主さんも多いはずです。原因によって必要なケアは異なりますが、まずは愛犬が安心して過ごせる環境を整えることが大切です。
ここでは、老犬が快適に呼吸できるようにする具体的な対処法を紹介します。
楽な姿勢を取らせる
老犬がハァハァと呼吸しているときは、まず呼吸がしやすい姿勢をとらせることが大切です。胸やお腹への圧迫を減らすために、うつ伏せや横向きの姿勢にしてあげると肺が自然に広がりやすくなります。特に横向きで首が少し上がる姿勢は、気道が確保されやすく呼吸の負担を軽減できます。
呼吸が苦しそうな場合は、体を支えるためにタオルやクッションを背中や脇に入れて安定させるのも効果的です。逆に仰向けや固い床での姿勢は胸を圧迫して呼吸がさらに苦しくなるため避けましょう。
また、不安やストレスで呼吸が乱れている場合は、飼い主さんが優しく声をかけたり、そっと体に触れて落ち着かせてあげることも大切です。
室温・湿度の調整で快適な環境づくりを
老犬は体温調節が苦手なため、室温や湿度が高すぎると呼吸がさらに荒くなったり、体に大きな負担がかかることがあります。特に高温多湿の環境では、体内の熱をうまく逃がせず、ハァハァと浅い呼吸を繰り返す原因になります。
エアコンや扇風機、除湿機を上手に使い、室温はおおむね22〜25℃、湿度は50〜60%を目安に保つようにしましょう。直接風が当たらないように配慮し、涼しく穏やかに過ごせる空間を整えることが大切です。
また、季節や天候によって室内環境は大きく変化します。夏の冷房だけでなく、冬の暖房による乾燥や温めすぎにも注意が必要です。老犬が快適に呼吸できる環境を日々調整してあげることが、愛犬が穏やかに呼吸できる環境作りにつながります。
こまめな水分補給
脱水は呼吸が荒くなる原因のひとつでもあるため、老犬にはいつでも新鮮な水を飲める環境を整えてあげましょう。特にシニア期は体内の水分バランスを保つ力が弱まり、少しの脱水でも体調を崩しやすくなります。
一度にたくさん飲ませるのではなく、少量をこまめに与えることがポイントです。お湯で少し温めた水や、氷を入れて温度を調整するなど、飲みやすく工夫するのもおすすめです。
ただし、飲み込みが弱くなっている場合や、むせ込み・誤嚥(ごえん)が心配な場合は無理に飲ませず、獣医に相談してください。水分補給は熱中症の予防にもつながります。日頃から飲む量や回数を観察し、少しでも変化があれば早めに対応することが大切です。
症状が続く・悪化した場合は獣医師に相談を
老犬のハァハァとした呼吸がなかなか落ち着かない、あるいは時間が経つほどに荒くなっている場合は、迷わず動物病院へ相談しましょう。特に呼吸が苦しそう、舌や歯茎が青紫色になるチアノーゼ、ぐったりして立ち上がれないなどの症状が見られるときはできるだけ早く受診することが大切です。
老犬の呼吸異常は、心臓病や肺の疾患など命に関わるケースも少なくありません。早めに診察を受け、必要な検査や治療を行うことが、重症化を防ぐ最善の方法です。
また、定期的な健康診断で心臓や呼吸器の状態を確認しておくと、異常を早期に発見しやすくなります。日頃から呼吸の変化に注意を払い、少しでも異常を感じたら獣医の判断を仰ぎましょう。
老犬が暑くないのにハァハァするときのよくある質問

老犬が落ち着かない様子でハァハァと息を荒くしていると、理由がわからず心配になる飼い主さんも多いはずです。中にはすぐ病院へ行くべきか迷うケースもありますよね。この章では、そんなときに知っておきたい判断の目安や対処法を、よくある質問形式でわかりやすく解説します。
老犬が暑くないのにハァハァしていたら、すぐに受診すべきですか?
暑さ対策をしても呼吸が荒いまま改善しない、安静にしてもハァハァが止まらない場合は、早めに動物病院を受診しましょう。呼吸数が異常に多い、舌や歯茎が青や白っぽい、ぐったりして立ち上がれないといった症状があるときは特に注意が必要です。
これらは呼吸器や心臓の異常が進行している可能性があり、放置すると危険です。迷ったときは自己判断せず、すぐに獣医に相談しましょう。
息が苦しそうなとき、安静にさせるだけで大丈夫ですか?
呼吸が少し速い程度で、落ち着いていれば静かな場所で安静にさせて様子を見ることも有効です。周囲の音や刺激を減らし、リラックスできる環境を整えてあげましょう。
ただし、呼吸がどんどん浅くなる、ヒューヒューと異音がする、伏せることができない、不安そうに落ち着かないなどの様子が見られる場合は注意が必要です。安静にして様子を見るだけでは危険な場合もあるため、早めに動物病院へ連絡し、指示を仰ぐようにしましょう。
老犬がハァハァしているときは無理に動かさないほうが良いですか?
老犬は年齢とともに心肺機能や筋力が低下するため、無理に動かすと疲労や呼吸困難を悪化させるおそれがあります。専門家も、息が荒いときはうつ伏せなど呼吸がしやすい姿勢で安静にさせることを推奨しています。
過度な刺激や運動を強いるとストレスとなり、症状を悪化させることもあるため、落ち着いた環境でそっと休ませてあげましょう。
食後いつもハァハァしているのは大丈夫ですか?
食後にハァハァと呼吸するのは、食事によって体温が上がったり、満腹で一時的に呼吸が速くなることが原因の場合もあります。少し休んで呼吸が落ち着くようであれば、基本的に心配はいりません。
しかし、毎回食後に荒い呼吸が長く続く、苦しそうにしている、食欲や元気がないといった様子がある場合は注意が必要です。消化器や気管、心臓の疾患が隠れている可能性もあります。頻繁に繰り返すときは早めに動物病院を受診し、原因を確認してもらいましょう。
安静時でもハァハァが止まらないときは危険ですか?
安静にしていてもハァハァと浅い呼吸が続き、口を大きく開けて苦しそうにしている場合は、呼吸器や心臓の重い病気の可能性があります。
特に舌や歯茎の色が青紫色になる、呼吸のたびに肩が大きく動く、体を起こしたまま眠れないといった症状が見られるときは要注意です。これらは酸素不足の危険なサインで、放置すると命に関わることもあります。自己判断で様子を見ず、できるだけ早く動物病院へ受診してください。
まとめ

老犬が暑くないのにハァハァしている場合、ストレスや運動後の反応、加齢による呼吸機能の低下などが原因として考えられます。しかし、中には肺炎や心臓病などの深刻な病気が隠れていることもあります。
普段から呼吸の速さや浅さ、舌の色、行動の変化を観察し、異常が続くときは早めに獣医へ相談しましょう。室温や湿度の管理、こまめな水分補給などの対策で、愛犬が少しでも健康に、そして大好きな飼い主さんと安心して過ごせる時間を作ってあげてくださいね。


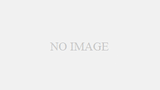

コメント