年を重ねてきた愛犬の咳が止まらない様子を見ると、「慢性気管支炎になってる?」「具合が悪くなければ良いけれど」と不安に感じる事もあるのではないでしょうか。
年齢を重ねるにつれて体の調子が変化しやすく、心臓や慢性気管支炎など呼吸器系のトラブルが隠れている可能性も増えてきます。一見ただの空咳に見えても、愛犬の体には思っている以上の負荷がかかっている場合もあります。
本記事では、咳のパターンや音の特徴、考えられる症状をわかりやすく整理。さらに、病院に相談すべきタイミングや、日常でできる対応策まで、優しくお伝えします。
慢性気管支炎による咳は特に注意が必要
「慢性気管支炎」とは、気道(気管や気管支)に慢性的な炎症が続き、2カ月以上にわたって咳が続く状態を指します。とくに老犬では、加齢によって気道の粘膜が弱くなり、長引く咳が起こりやすくなります。
この病気のやっかいな点は、一見元気に見えても、肺や気管にダメージが蓄積していくことです。咳が習慣のようになっていても、「年のせいかな」と見過ごしてしまいがちですが、慢性気管支炎は放っておくと、呼吸がしにくくなったり、気管が変形してしまう可能性もあります。
また、慢性気管支炎を抱えている犬は、気温の変化や湿度の影響で咳が悪化することもあります。生活の質(QOL)を大きく下げる病気であるため、早めの診断と治療が重要です。
咳が毎日出ていても、元気や食欲があるからといって安心せず、「慢性的な咳」は病気のサインとして向き合ってあげることが大切です。
慢性気管支炎になった時の治療法
慢性気管支炎と診断された場合、治療の目的は「咳を和らげること」と「炎症の進行を抑えること」です。完治は難しいものの、適切な治療で症状をコントロールすることは可能です。主な治療方法として次のようなものがあげられます。
- 気管支拡張剤の投与
- ステロイド薬の使用
- 咳止め薬の処方
- ネブライザー(吸入治療)の導入
気管支拡張剤は、気道を広げて呼吸を楽にし、咳の頻度を軽減します。ステロイド薬は気道の炎症を抑える目的で使われ、通常は少量からスタートして、愛犬の様子を見ながら調整されます。咳止め薬は、咳によって眠れない・食事ができないなど生活に支障が出ている場合に処方されますが、無理に咳を抑えるのが逆効果な場合もあるため、獣医師の判断が重要です。
また、ネブライザーと呼ばれる吸入治療器を使い、薬剤を気道に直接届ける方法もあり、自宅で管理できるケースもあります。
治療とあわせて、室内の加湿・掃除・ストレス軽減などの生活環境の見直しも忘れずに行いましょう。愛犬の症状に合わせたケアを続けることで、少しでも快適な日常を取り戻すサポートができます。
慢性気管支炎によくある原因
慢性気管支炎は、犬の気管支に炎症が長く続くことで起こる病気です。特に老犬によく見られますが、その原因はひとつではありません。
代表的なものに長期間にわたる空気中の刺激物(タバコの煙やハウスダストなど)があります。また、過去の感染症やアレルギー反応がきっかけとなり、気道に慢性的な炎症が残ることもあります。寒暖差や乾燥、ストレスなどの環境要因が悪化の引き金になるケースもあるため、生活環境の見直しも重要なポイントです。
原因が特定できないこともありますが、早めの対応で進行を遅らせることは十分に可能です。
老犬の咳が止まらない時によくある原因
年齢を重ねた愛犬が咳をするようになったら、「年のせい」と見過ごさず、体の不調サインとして受け止めることが大切です。
シニア期には慢性気管支炎や気管虚脱などの呼吸器の病気が現れやすく、乾いた咳やガーガーという音が見られることも。また、心臓の機能低下によって肺に水がたまり、咳が出るケースもあります。
さらにアレルギーや異物の誤飲、腫瘍などが原因となることもあるため注意が必要です。咳の出方や頻度、体調の変化を記録しておくと、動物病院での診断に役立ちます。気づいたときに早めの対応をすることが、愛犬の健康を守る第一歩になります。
呼吸器系の病気
老犬に見られる咳の原因として、以下のような呼吸器系の病気が考えられます。
- 慢性気管支炎
- 気管虚脱
- 肺炎
- 副鼻腔炎(ふくびくうえん)
- 肺水腫(はいすいしゅ)
慢性気管支炎
高齢の犬に多く見られる代表的な呼吸器疾患です。
気管支の内側に炎症が長く続き、「カハッカハッ」と乾いた様な咳を特徴としています。特に朝起きた直後や、運動後に強くなる咳が出る傾向です。初期のうちは元気や食欲に大きな変化がないことも多く、注意して見ていないと見逃されやすい病気。治療せずに放置すると、炎症が悪化し肺への負担が増し、やがて呼吸がしづらくなることもあります。
気管虚脱
気管の構造が変形する事で、呼吸の際に空気の通り道が狭くなってしまう状態です。
小型犬や老犬が特に発症しやすく、「ゼーゼー」「ガーガー」等の苦しげな咳を特徴としています。興奮したときやリードを強く引いたとき、または運動のあとに悪化することも。重症化すると呼吸困難を起こすこともあり、場合によっては手術の適応となるケースもあります。
肺炎
ウイルスや細菌の感染によって肺に炎症が起きる病気です。
湿って痰の絡むような「ゴホゴホ」という咳が続きます。熱が出たり、食欲がなくなったり、ぐったりして元気がないといった症状が同時に見られることが多く、進行すると酸素が足りなくなる危険性が潜んでいる病気です。早めの治療が重要です。
副鼻腔炎
鼻の奥にある「副鼻腔」という部分に炎症が生じ、咳につながることがあります。
鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどと一緒に現れることが多く、鼻から喉に流れた粘液が咳の刺激になるケースもあります。特にアレルギー体質の犬では慢性化しやすいため、繰り返す場合は注意が必要です。
肺水腫
主に心臓疾患の影響で、肺に水分がたまってしまう重篤な状態です。咳のほか、「呼吸が荒くなる」「口を開けて必死に息をしようとする」など、呼吸の異常が目立つようになります。舌の色が紫がかる(チアノーゼ)といった症状も命に関わるサインです。こうした兆候が見られた場合は、一刻も早く動物病院を受診する必要があります。
老犬の場合、こうした病気が単独ではなく複数同時に進行している(併発している)ケースも珍しくありません。咳の種類やタイミングをしっかり観察し、早めに獣医師に相談することが重要です。
心臓の病気
- 僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)
- 心不全
- 肺水腫(心原性)
僧帽弁閉鎖不全症
高齢の小型犬に特に多く見られる心臓の病気で、心臓の左側にある僧帽弁がうまく閉じなくなり、血液が逆流することで心臓や肺に負担がかかるようになります。この影響により、乾いた咳や痰が絡んだような咳が出ることがあります。症状が軽い初期段階ではあまり目立ちませんが、進行すると咳の頻度が増えたり、散歩中に疲れやすくなったりするなどの変化が現れてきます。
心不全
心臓全体の働きが弱まり、血液を全身に送り出す力が低下している状態です。
その結果、肺や腹部などに水分がたまりやすくなり、呼吸に異常が出ることもあります。浅く速い呼吸、眠りが浅くなる、横になるのを嫌がる、舌が紫がかるなどの症状が見られる場合には、早期の治療が不可欠です。内服薬を中心とした継続的な管理が必要になる病気です。
肺水腫(心原性)
心臓の不調が原因で肺の中に水分がたまることで起こります。
呼吸が苦しそうになり、咳とともに泡状の痰を吐くような様子が見られることがあります。特に「ガーガー」と苦しげな呼吸音が出る場合には、命に関わる状態に近づいていることも。明らかな呼吸の異変を感じたら、ためらわずにすぐ動物病院を受診しましょう。。
咳が出ているだけでは「心臓病」とは分かりにくいため見逃されやすいのが特徴です。「元気がない」「疲れやすい」などのささいな変化にも気づいてあげることが大切です。
その他
- アレルギー
- 異物の誤飲
- 腫瘍
- 逆くしゃみ
アレルギー
身の回りの環境に含まれるホコリ、花粉、香料、煙などが刺激となり、気道に反応が起きて咳を誘発することがあります。アレルギー体質の犬は敏感で、少しの刺激でも強く反応する場合があります。咳のほかに、くしゃみや目のかゆみ、皮膚を掻く行動が見られることもあります。
異物の誤飲・誤嚥
食べ物やおもちゃの破片などが誤って気管に入り込んだ場合、むせるような咳が出ることがあります。
老犬は嚥下機能が低下していることが多く、誤嚥しやすい傾向にあります。短時間で咳が止まれば問題ないこともありますが、続くようであれば異物が残っている可能性があるため、早めの対処が必要です。
腫瘍
肺や気道の近くに腫瘍ができると、その部分を圧迫し、慢性的な咳を引き起こすことがあります。咳の変化が急に目立つようになったり、血の混じった痰が出る場合には、精密検査が必要になります。
腫瘍の場所や大きさによっては、外見からは分かりにくいこともあるので注意が必要です。
逆くしゃみ
とくに小型犬で見られる、鼻の奥に刺激が入ったときに起こる反射的な動作です。フガフガと鼻から空気を吸い込むような音を立て、初めて見ると咳に似て驚くかもしれませんが、これは生理的な現象であることがほとんどです。
ただし、回数が急に増えた場合には他の疾患が関係している可能性もあるため、一度相談してみると安心です。
シニア犬の場合は併発することもある
年齢を重ねた犬は、体のさまざまな部分に少しずつ負担が蓄積されやすくなり、ひとつの病気だけでなく複数の不調が同時に起きる「併発」が見られることもあります。若い頃であれば単体で済んでいた病気も、シニア期には他の疾患と重なって進行するケースが少なくありません。
たとえば、「慢性気管支炎」と「僧帽弁閉鎖不全症」のように、呼吸器と心臓に関わる病気が同時に進行していると、咳がよりひどくなったり、治療薬の効果に影響が出ることもあります。また、「気管虚脱」と「肺炎」など、ひとつの病気が別の病気を悪化させるパターンもあるため、外見以上に体にかかる負担は大きくなります。
こういった背景から、咳が出ている場合には「ひとつの原因」だけでなく、複数の可能性を考えることが大切です。症状が長く続いていたり、複雑に見えるときには、「とりあえず咳止めを与える」という判断ではなく、血液検査やレントゲンなどの精密な検査を受けることで、適切な治療につなげることができます。
さらに、シニア犬は気温差や湿度の変化にも敏感です。季節の変わり目や梅雨時期、寒暖差の大きい日などは、体調を崩しやすい時期でもあります。少し息が荒い、咳が増えた、寝苦しそうにしているなど、日常の中の小さな変化を見逃さず、早めに気づいてあげることが重症化の防止につながります。
日々の体調をこまめに観察し、定期的に健康チェックを行うことで、老犬の穏やかな毎日を支えていけるとよいですね。
老犬の咳が止まらない時にすべき対処法
シニア犬の咳を続ける様子は、「年齢のせいかな」と様子を見たくなる気持ちもありますが、放置したまま病気が進行する危険性も潜む怖い症状です。特に心臓・呼吸器に咳の原因がある時には、早期に対処することで負担を軽減できる可能性が十分にあるので的確な判断が大切です。
咳が止まらないときに、飼い主さんがすぐにできる行動には、「症状がどういったなもかの記録」と「迅速に病院へ連絡する」が基本。ここでは、具体的なポイントを詳しくご紹介していきます。
犬の症状のメモや動画を撮る
まずは咳の出方やタイミング、頻度をじっくりと観察し、できるだけ客観的に記録する事が重要となります。次のような症状。状態をメモに残すと診察時に役立ちます。
- 咳の出る時間帯(朝・夜・運動後等)
- 咳の種類(乾いた咳なのか、痰がからんだような音がする等)
- 咳の持続する時間や1時間の咳回数
- 呼吸の様子(荒い・浅い・お腹で息をしている等)
- 食欲・元気の有無、体調の変化
文字だけでは伝えにくい状況の時には、スマートフォンを使用し咳の様子を動画に残しておくと、より性格に伝えることができます。特に動物病院では、診察室では咳が出ないこともあるため、こうした記録によりスムーズな診断を受ける手助けが出来ます。
また、同時にくしゃみ・鼻水・呼吸音などがある場合は、それらもあわせてメモしておくとよいでしょう。
病院に電話し、診察を受ける
症状の観察ができたら、早めにかかりつけの動物病院に連絡し、状況を伝えましょう。すぐに診察が必要か、様子見でよいかを電話で判断してもらえる場合もあります。咳が続いていること、回数が増えてきたこと、呼吸に異常が見られることなどを、なるべく具体的に伝えるのがポイントです。
- 以下のような症状がある場合は、できるだけ早く受診することが推奨されます。
- 咳と同時に呼吸が苦しそう
- 舌が紫っぽく見える(チアノーゼ)
- 咳のたびに体を縮めている
- 咳の回数が急に増えた
- 食欲や元気が著しく低下している
診察時には、前述のメモや動画を持参することで、よりスムーズに症状を伝えることができます。また、既に持病がある場合や、服用中の薬があればその情報も一緒に伝えるようにしましょう。
老犬は、ほんの少しの体調変化でも大きな負担になります。早めの行動と、丁寧な情報提供が、愛犬の命を守る第一歩となります。
焦る必要のない老犬の咳
咳が出たからといって、すぐに病気になるとは限りません。以下のような原因による咳は、一時的なものであることが多く、基本的には焦る必要はありません。
水や食べ物が気管に入ったとき
食後すぐに「カハッ」と咳をすることがありますが、これは誤嚥(ごえん)しかけた際の生理的な反応で、すぐに治まれば問題ありません。
興奮したときやリードを強く引いたとき
お散歩中にリードが首輪に食い込むと、咳き込むことがあります。こうした咳は首への圧迫によるもので、深刻なものではありません。
乾燥やホコリによる一時的な刺激
空気の乾燥もしくはハウスダストによる刺激が、単発的な咳を誘発することもあります。換気や加湿で改善しやすい為、気になる方はまずは換気をしてみましょう。
これらが原因で出現する咳症状は、いずれも一過性であり継続的に続かない事が特徴です。ただし、同様の咳が頻繁に出るようになったり、体調の変化が見られた際には、一度病院で相談すると安心できますよ。
緊急性の高い老犬の咳
一方で、以下のような咳症状が出現した際には、緊急性が高くすぐに動物病院を受診しましょう。
- 咳と同時進行で呼吸も苦しくなっている
ゼーゼー・ハアハア等の呼吸音がある場合は肺又は心臓に深刻な問題がある可能性 - 舌もしくは歯ぐきが紫色に見える(チアノーゼ)
酸素不足のサインで、命にかかわる状態。至急の対応が櫃お湯 - 夜間を中心に咳症状が悪化し、眠れない様子を見せている
心臓病や肺水腫が原因のことが多く、早めの治療が必要 - 咳と同時にぐったりしている、食欲の低下
体力が落ちている中での咳は体全体に大きな負担となっている可能性
このような症状がある場合、自己判断は危険を伴います。一見落ち着いて見えても、内臓に大きな問題を抱えているケースもありますので、すぐに病院へ連絡し、診察を受けるようにしましょう。
老犬の咳に関するよくある質問
老犬の咳が続いていると、「この咳は大丈夫なのかな」「すぐ病院に行くべき?」と、いろいろな不安や疑問がわいてくるものです。特に初めてこうした症状を目の当たりにした飼い主さんにとっては、ちょっとした咳でも心配になりますよね。
ここでは、老犬の咳に関してよく寄せられる質問と、それぞれの疑問に対するわかりやすい解説をまとめました。
気になる症状がある方も、今は大丈夫だけれど備えておきたいという方も、ぜひ参考にしてみてください。
老犬が「カハッ」とするような咳をします。これは病気ですか?
「カハッ」という音を伴う咳は、乾いた空咳や逆くしゃみ、または気管支系の病気によって起こることがあります。一時的なものなら問題ないこともありますが、毎日何度も繰り返すようであれば、慢性気管支炎や気管虚脱などが疑われます。とくに寝起きや運動後に咳が出る場合は、早めに獣医師の診察を受けることをおすすめします。
痰がからんだような音の咳が続いています。放っておいて大丈夫ですか?
「ゴホッ、ググッ」と痰がからんでいるような音がする咳は、気管や肺に炎症がある可能性があります。慢性気管支炎や肺炎などが原因になっていることもあり、放置すると悪化するリスクがあります。老犬は自己治癒力が弱まっているため、湿った咳が数日続く場合は受診が必要です。
老犬の気管支炎は治るのでしょうか?
慢性気管支炎は、完全に治すことが難しい病気ですが、薬や生活環境の工夫で症状をコントロールすることは十分可能です。気管支拡張薬や抗炎症薬などを使って、咳を軽減したり呼吸を楽にしたりする治療が一般的です。早期発見と継続的なケアによって、愛犬の生活の質を保つことができます。
咳止めを与えたらすぐに治りますか?
咳止めは、咳の症状を一時的に和らげるために使われることがありますが、原因となる病気を治すものではありません。また、咳が体にとって必要な防御反応である場合、無理に止めることが逆効果になることもあります。獣医師の判断のもと、病状に合った薬を使うことが大切です。自己判断で人間用の咳止めを与えるのは絶対に避けてください。
気管虚脱ってどんな病気ですか?どの犬に多いですか?
気管虚脱は、気管がつぶれるように変形し、呼吸がしづらくなる病気です。とくに小型犬やシニア犬によく見られ、「ガーガー」もしくは「カハッ」といった咳が特徴です。咳は運動後や興奮時に悪化する傾向があります。軽度であれば内服薬での管理が可能ですが、重度の場合は外科的な治療が必要となることもあります。
まとめ
老犬の咳症状は、加齢にともなう生理的な反応で出現している事もあります。しかし気管支炎や気管虚脱・心臓病などの病気が関係していることも少なくありません。
「ただの咳」と見過ごさず、症状の変化を観察し、必要に応じて動画やメモをとって早めに獣医師に相談することが大切です。
慢性気管支炎のように、症状が長引く場合でも適切な治療によって生活の質を保つことは可能です。
日々の体調の変化に丁寧に寄り添いながら、愛犬が穏やかに過ごせるよう、飼い主さん自身も安心して対応できるように備えてく事が大切です。



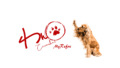
コメント