長年一緒に過ごしてきた愛犬が、急に立てなくなる姿を見ると驚きと不安でいっぱいになります。
しかし、原因は多岐にわたるのも事実。老犬の場合、寿命が近づいていることもあれば、病気や一時的な体調不良が原因のこともあります。立ち上がれないとトイレが難しくなったり、留守番中に転んでしまったりと生活にも影響が出てきます。そんな時、飼い主ができるのは適切な補助や環境の工夫です。
そこで今回は、老犬が立てなくなる原因や見分け方、日常生活での具体的な対策までわかりやすく紹介します。
犬(老犬)が急に立てなくなる原因は?

犬(老犬)が急に立てなくなる原因は多岐にわたります。
ここでは主な原因である骨折や捻挫(ねんざ)などのケガ、神経の病気、椎間板ヘルニア、そして加齢による筋肉の低下といった原因について、それぞれ解説しましょう。
骨折や捻挫などのケガ
犬が急に立てなくなる原因のひとつに、骨折や捻挫といったケガがあります。とりわけ小型犬は骨が細く、ソファやベッドからの飛び降りなどの些細な動作で骨折することがあります。
骨折や捻挫を起こすと、犬は痛みのために足を地面につけられず、立ち上がろうとしてもすぐに座り込んでしまうことが多いです。それに、患部に腫れや熱感が見られたり、歩こうとすると足をかばう仕草をすることも特徴です。
シニア犬では骨がもろくなっているため、軽い衝撃でも骨折や関節の損傷を起こしやすく注意が必要です。もし愛犬が急に足を引きずり始めたり、強い痛みを訴えているようであれば、無理に動かさずに安静にし、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。
早期に診断と治療を受けることで、回復が早まり後遺症を防ぐことにもつながります。
神経の病気
犬が立てなくなる原因として、神経に関わる病気もあり得ます。
代表的なものに「変性性脊髄症」や「ウォブラー症候群」などがあり、いずれも神経の伝達がうまくいかなくなることで足の麻痺やふらつきが起こります。
神経疾患は初期段階では軽いふらつきや後ろ足のもつれといった症状がみられ、さらに進行すると自力で立ち上がれなくなることがあります。
とりわけ大型犬に多く、加齢とともに発症リスクが高まるのが特徴です。
神経の病気は骨折や捻挫と違い、外見では判断しづらいことが多いので、歩行の異常や姿勢の変化を見逃さないよう注意するようにしましょう。進行性の病気で完治が難しいケースもありますが、早めに発見して治療やリハビリを行うことで進行を遅らせ、生活の質を保ちやすくなります。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板が変性して神経を圧迫する病気で、とりわけダックスフンドやコーギーなど胴長短足の犬種に多くみられます。初期症状として見られるのは歩き方がぎこちなくなったり、背中を丸めて痛そうにする様子、さらに進行してしまうと後ろ足に力が入らなくなり、急に立てなくなることがあります。
軽度の場合は安静と投薬で回復が期待できますが、重症化すると手術が必要になるケースもあります。椎間板ヘルニアは再発しやすいため、発症後は生活環境にも注意が必要です。
例えば滑りやすい床を避けたり、段差の昇り降りを制限するなど、日常生活で負担を減らす工夫が大切です。もし愛犬が急に動けなくなった場合は放置せず、できるだけ早く獣医師に相談するようにしましょう。
加齢による筋肉の低下
老犬が急に立てなくなる原因には、加齢による筋肉の衰えが大きく関係しています。
年齢を重ねると徐々に運動量が減り、筋力が少しずつ低下していきます。衰えた結果、立ち上がる時に足に力が入らず、転びやすくなるのです。
また、関節の変形や慢性的な痛みがある場合も、動きが制限され立ち上がれなくなる原因に。筋肉の低下は急に起こるものではありませんが、ある日を境に目立つようになることも多く、飼い主にとっては「突然動けなくなった」と感じられることも珍しくありません。
加齢で立てなくなる予防としては、若いうちから適度な運動を続けること、老犬期になったら無理のない散歩や関節に優しいフード・サプリを取り入れることが良いとされています。
ただ、愛犬の様子に変化が見られたら、筋力の低下だけでなく病気の可能性もあるため、獣医師に相談するのがおすすめです。
脳疾患
犬が急に立てなくなる原因のひとつに、脳のトラブルがあります。代表的な脳疾患は脳梗塞や脳出血、脳腫瘍、てんかん発作などです。脳疾患は脳から体への指令がうまく伝わらなくなり、足に力が入らなかったり、バランスを崩して立てなくなったりすることがあります。
脳梗塞や脳出血では、急に片足だけ動かなくなったり、歩き方がフラフラになったりするのが特徴。てんかんの場合は、痙攣したあとしばらく立ち上がれないこともあります。
老犬では脳腫瘍のリスクも高くなるため、普段と違う動きやふらつき、ぼんやりしている様子が見られたら注意が必要です。脳の病気は早めに対応できるかどうかで今後が変わってくるので、「おかしいな」と思ったら無理に動かさず、できるだけ早く動物病院に相談するのが安心です。
犬(老犬)が急に立てなくなった時の対処法

「昨日まで元気に歩いていたのに、今朝になったら立ち上がれない…」そんな状況に直面すると、とても不安になります。
老犬が急に立てなくなるのは、病気やケガ、筋力の低下などさまざまな原因が考えられます。
大切なのは、焦らずに適切な対処をしてあげることです。ここでは、老犬が急に立てなくなったときに飼い主ができる主な対処法を、具体的にわかりやすく解説します。
まずは動物病院を受診する
老犬が急に立てなくなったら、まずは動物病院に連れて行くことが最優先です。骨折や神経疾患、脳や心臓のトラブルなど、命に関わる病気が隠れている可能性もあるからです。それに何が原因で立てなくなったのかを判断してもらうことも重要です。
「しばらく様子を見よう」と思ってしまいがちですが、急な変化は緊急性が高い場合が多いため、できるだけ早く獣医師に診てもらいましょう。
受診の際は、発症の様子や普段との違い、呼吸の状態、食欲などをメモして伝えると診察がスムーズです。動物病院では身体検査のほか、レントゲンや血液検査などで原因を探ってくれます。
場合によっては入院や治療が必要になることもありますが、早期発見・早期対応で改善が期待できるケースも少なくありません。
適度な運動を促す
病気の緊急性が否定され、加齢による筋力低下が原因の場合は、適度な運動がとても大切です。いきなり激しい運動をする必要はなく、散歩の時間を短めにしたり、平らな場所を歩かせたりするだけでも効果があります。
無理なく筋肉を使うことで、残っている筋力の維持や回復につながります。また、滑りやすい床ではフローリングマットを敷いてあげると、足腰に負担をかけずに歩きやすくなります。水中ウォーキングや軽いストレッチなど、動物病院でリハビリ指導を受けられるケースもあるので相談してみてもよいでしょう。
ただし、痛みや息切れが見られる場合は運動を控え、必ず獣医師に相談することが大切です。
自宅でリハビリをさせる
神経疾患や筋力低下が原因の場合、自宅でできるリハビリも効果的です。たとえば、後ろ足をやさしく曲げ伸ばしするストレッチや、補助ベルトを使っての歩行練習などがあります。
飼い主さんが体を支えながら少しずつ歩かせるだけでも、筋肉や神経に刺激を与え、回復を助ける効果があります。リハビリは毎日少しずつ継続することが大切ですが、無理をさせると逆効果になることも。犬が嫌がったらすぐに中止しましょう。
また、リハビリ方法は犬の状態や病気によっても変わるため、自己判断せず獣医師やリハビリを扱う動物病院に指導してもらうと安心です。家庭でできる工夫を取り入れることで、犬の生活の質を少しでも維持できるでしょう。
食事を変更する
老犬が立てなくなったときには、食事の見直しも大事なサポートになります。筋肉を維持するには良質なたんぱく質が欠かせませんし、関節の健康を考えるとグルコサミンやコンドロイチンを含むフードやサプリメントもおすすめです。
また、便秘で踏ん張れなくなっている場合は、食物繊維や水分を多く含む食事に変えることで排便が楽になります。
さらに、肥満は足腰の負担を増やす大きな要因なので、体重管理も大切なポイント。フードの量や内容を調整し、必要に応じて療法食に切り替えるのも効果的です。ただし、急な食事の変更は消化不良の原因になるため、必ず獣医師と相談しながら少しずつ切り替えていくようにしましょう。
犬(老犬)が急に立てなくなって動物病院に行った時の検査は3種類

老犬が急に立てなくなったときはまず動物病院へ連れていきます。
そして原因を探るには、病院での検査が欠かせません。診察では問診・身体検査、血液検査、画像検査の3つを組み合わせて行うのが一般的です。
ここでは、それぞれの検査で何がわかるのか、どんな目的で行われるのかを詳しく解説します。
問診・身体検査
病院に着いて最初に行うのが問診と身体検査。ここでは、飼い主さんから発症のタイミングや普段との違いを聞き取り、獣医師が犬の意識や歩行状態、呼吸や心音をチェックします。例えば突然立てなくなったのか徐々に弱ってきたのかによって、疑われる病気が変わります。
また、発作の有無や誤食の可能性なども重要な手がかりです。身体検査では神経反射の確認や足先の感覚テストなどを行い、神経疾患か整形外科的な問題かを見極めます。
この段階で重症度の目安がつくため、命に関わる状態なら検査より先に緊急処置を優先することもあります。問診・身体検査はその後の検査内容を決める大切な第一歩なんです。
血液検査
血液検査は、体の中で起きている異常を幅広く調べられる基本的な検査です。たとえば貧血や炎症反応、肝臓や腎臓の数値、血糖値、電解質のバランスなどをチェックすることで、全身状態の把握が可能。老犬では糖尿病や腎不全、感染症などが立てなくなる原因になることも少なくありません。
血液検査の結果から、すぐに点滴が必要なのか、薬で調整できるのかといった治療方針が見えてきます。採血は短時間で済み、体への負担も比較的少ないため、緊急時にも実施されやすい検査です。
検査項目の範囲によって費用は異なりますが、1〜2万円ほどが目安とされています。
画像検査
骨や内臓、神経の状態を調べるためには画像検査が欠かせません。代表的なのはX線検査と超音波検査で、それぞれに得意分野があります。X線検査では骨折や関節の異常、胸部や腹部の大まかな臓器の様子を確認できます。
一方、超音波は心臓の動きやお腹の中の臓器の詳細をリアルタイムで観察するのに最適。
さらに必要に応じてCTやMRIといった高度な検査を行うことで、椎間板ヘルニアや脳疾患などもより正確に診断できます。体重や検査内容によって費用は変わりますが、小型犬ならレントゲンと超音波を合わせて2万円前後が目安です。
画像検査は原因の特定に直結する重要なステップになります。
犬(老犬)が立てなくなった時に起こりうる問題点

老犬が急に立てなくなる状態の裏には、体力の低下や病気、老化による多くの要因が隠れていることもあります。そして立てないまま過ごすことで、日常生活にもいろいろな影響が出てきます。
ここでは、特に注意しておきたいトイレの問題、床ずれ、筋力低下に分けて、起こりうるトラブルや対応のポイントを解説します。
トイレに補助が必要になる
老犬が自力で立てなくなると、まず困るのがトイレです。
今まで自分で歩いていた子でも、突然立てなくなると排泄のたびに飼い主がサポートしなくてはいけません。支えなしでは座ったまま排泄して体が汚れてしまうことも多いので、犬にとってもストレスになります。
とりわけ老犬は腎臓や膀胱の働きが弱って頻尿になる子も多いので、飼い主の負担は一気に増えるんです。
排泄が難しくなった場合は、トイレシートを広めに敷いたり、介護用のハーネスやオムツを使ったりすると少し楽になります。大切なのは「犬も飼い主も無理をしない工夫」を取り入れること。ほかにも日常的に体を拭いて清潔を保つことも忘れずに行いましょう。
床ずれが起きる
立てない状態が長く続くと、同じ姿勢で寝たきりになる時間が増えます。すると体の一部に圧力がかかり続けて床ずれができやすくなるんです。
とりわけ骨の出っ張った腰や肘、肩あたりは要注意。床ずれは一度できてしまうと治りにくく、犬にとっても強い痛みや不快感を伴います。さらに悪化すると感染症のリスクまで出てきてしまいます。
対策としては、犬用の介護ベッドや低反発マットを用意して体への負担を減らすこと、数時間おきに体勢を変えてあげることがポイントです。また、こまめに体を触って異変がないかチェックする習慣をつけるのも大切です。
床ずれは予防が第一といえるトラブルなので、立てなくなった時点で早めの対策を始めることをおすすめします。
運動不足になり、筋力が低下する
立てなくなってしまうと、当然ながら自分で歩いたり動いたりすることが難しくなります。その結果、運動不足によって筋肉がどんどん落ちていき、ますます立ち上がれなくなるという悪循環に陥りやすいんです。
老犬はただでさえ筋力や関節の動きが衰えているので、動かない時間が続くほど体の回復が難しくなってしまいます。
筋力の低下を防ぐには、飼い主のサポートで少しでも体を動かすことが大切。介護用ハーネスで支えて歩かせたり、寝たままでも手足を優しくマッサージしたり、関節をゆっくり動かすリハビリ運動を取り入れると効果的です。
完全に元のように歩けなくても、少し動かすことが筋肉の維持や血流改善につながり、犬の生活の質を保つことにつながります。
犬(老犬)が踏ん張れなくなることを防止する方法

老犬になると、筋力や関節が衰えて踏ん張る力が弱くなりがちです。そのせいで立ち上がれなかったり、トイレやお散歩が大変になったりすることもしばしば。
でも、ちょっとした工夫や運動、サプリでサポートすれば、老犬でも踏ん張る力をある程度キープできます。日々の生活の中でできることを少しずつ取り入れるだけで、愛犬の動きや体調に差が出てきます。
ここでは、無理なく続けられる簡単な方法をいくつか紹介します
適度な散歩や水泳を取り入れる
老犬の筋肉や関節を守るには、無理のない運動がとにかく大事です。
毎日の短め散歩でも、筋肉を刺激して踏ん張る力をサポートできますし、歩くことで血流も良くなり、関節や内臓にも良い影響があります。
また、水泳は関節に負担をかけず全身を使えるので、特に関節が弱い犬や重めの犬にもおすすめです。水の浮力で体重の負担が減るので、無理なく筋力維持ができます。
ただし、疲れすぎたり無理に泳がせたりすると逆効果になるので、呼吸や動きの様子をしっかり見ながら時間や回数を調整しましょう。
楽しみながら続けることが、長く踏ん張る力を保つポイントです。
犬種に応じてヘルニア対策をする
踏ん張れなくなる原因のひとつに、椎間板ヘルニアや腰のトラブルがあります。中でもダックスフンドやコーギーなど、ヘルニアになりやすい犬種は注意が必要です。ジャンプや階段の昇降を減らしたり、滑りにくい床材に変えたりして、腰や背中に負担をかけない環境作りをしてあげましょう。
抱っこする時も背骨や腰を支えるように注意すると安心です。また、急に走らせたり、無理に持ち上げたりするのは避けることが大切です。定期的に動物病院でチェックを受けることで、ヘルニアや腰のトラブルを早期に発見でき、踏ん張る力を守る助けにもなります。
生活環境の工夫とケアの組み合わせがポイントです。
サプリメントを導入する
筋肉や関節をサポートするサプリは、老犬の踏ん張る力を守るのにかなり役立ちます。グルコサミンやコンドロイチン、MSM(メチルサルフォニルメタン)などは関節ケアにおすすめですし、タンパク質やアミノ酸が入ったサプリは筋力維持にもつながります。
老犬になると自然と筋肉量が減るので、運動だけで補うのが難しい場合にサプリが助けになってくれます。
ただし、犬の年齢や体調によって合うものは変わるので、導入前には必ず獣医さんに相談して選ぶのが安心です。運動と組み合わせて使うことで、より踏ん張りやすい体を長く保てる可能性が高まります。
日々の生活に取り入れやすいものを選ぶのがコツです。
老犬が急に立てなくなる時によくある疑問

愛犬が立てなくなってしまうと、何をしたら良いのか、どの様な対応をすれば正解なのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、老犬とともに過ごしている飼い主が疑問に思うことをまとめ、わかりやすく解説しています。
犬が急に立てなくなったらまず何をすべき?
まずは慌てずに犬の様子を観察しましょう。呼吸や意識に異常がないか、痛がっていないかを確認し、必要であればすぐに動物病院へ連れて行きます。
急な麻痺やけいれん、立てないのにぐったりしている場合は緊急性が高いことも。抱っこや移動の際は、腰や首に負担をかけないようにタオルや毛布で体を支えると安心です。
犬が急に立てなくなって病院に行く時の必要な費用は?
診察費は動物病院によって異なりますが、初診料だけなら数千円程度。ただし血液検査やレントゲン、CTやMRIなどが必要になると1万円〜数万円かかることもあります。入院や治療が必要になるとさらに高額になる場合も。
事前にかかりつけの病院の料金体系を確認しておくと安心です。ペット保険に加入している場合は補償の範囲もチェックしておきましょう。
お漏らしをするようになったらどうすればいい?
立てなくなった犬は、自力で排泄できずにお漏らししてしまうことが増えます。無理に我慢させず、犬用オムツやトイレシートを活用すると飼い主の負担も減ります。
おしっこやうんちで体が汚れると皮膚トラブルにつながるので、こまめに体を拭いて清潔を保つことが大切です。頻尿や下痢が続く場合は泌尿器や消化器の病気の可能性もあるので、獣医さんに相談するのがおすすめです。
犬が立てなくなったら留守番はどうすればいい?
立てない犬を長時間ひとりにするのは危険です。転んだまま動けなくなったり、おしっこで体が汚れたりすることがあるからです。どうしても留守にする時は、短時間にとどめるか、家族やペットシッターに見てもらうのが安心です。
また、滑りにくいマットを敷いたり、サークルで安全なスペースを作ったりして、事故を防ぐ工夫をしましょう。
まとめ

老犬が急に立てなくなる姿を見ると「寿命が近いのでは」と心配になるものですが、実際にはケガや病気、筋力の衰えなど原因は多くあるのが事実です。
ただ、放っておくとトイレの介助や床ずれ、留守番中の事故といった生活面の負担も増えてしまいます。
だからこそ、まずは動物病院で原因を確かめることが大切です。そのうえで、サプリや適度な運動、補助グッズの活用、環境を整える工夫を取り入れていきましょう。
老犬にとって安心できる暮らしは、飼い主のサポート次第でぐっと変わります。焦らず寄り添いながら、少しでも穏やかに過ごせるように工夫してあげてください。



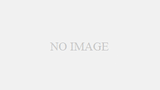
コメント